-
お問い合わせ
-
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
 |
衛生管理とは微生物との闘い!科学で安全を管理する
広島惣研株式会社 代表取締役一般社団法人HACCPと経営 代表理事光藤 清志(みつふじ きよし) |

食品を扱う企業にとって、最大の「危機(クライシス)」は何だと思いますか。
多くの方が、東北地方で製造された弁当による「食中毒」を思い浮かべたと思います。この食中毒は、黄色ブドウ球菌とセレウス菌によるもので、全国の29都道府県で500人を超える患者が確認されています。
食中毒の多くは下記の5点等が原因で発生したと推測されます。
食中毒事故が発生すると
食中毒事故が発生した瞬間に、企業のトップは名誉と利益を享受できる立場から、決断と義務、その結果に対する全責任を負う立場に一変します。
こうした事故に対し、保健所は営業禁止と原因の特定をして再開条件を示しますが、事業再開後の健全経営復活には関与しません。企業を助けてくれるのは、従業員とお客様だけですが、過去の食中毒事故をみますと、リスクマネジメントの欠如がクライシスを発生させ、結果として、廃業という従業員にとって悲しい結果が繰り返されているのが事実です。また、こうした事故だけでなく、食品クレームがクライシスを発生させ、企業の廃業という結果を招くこともあります。
食品による「クライシス」を起こさないために
企業を襲うクライシスは、天災を除けば何らかの予知が出来る場合が多くありますが、予知しようとする意識や体制がしっかりしていなければ、「無知」になってしまいます。
食品を扱う事業者、その従事者は、常時食品に関する苦情や食中毒事故を発生させてはならない、万一発生させたら取り返しがつかないことを再認識、再確認して、それぞれの職務を「事故を発生させない意識と緊張感」をもって確実に実施し、実施した具体的な衛生管理措置を記録、分析、保管して実施した措置をいつでも客観的に確認でき評価(振り返り)ができるようにしておくシステムがHACCPで、科学的な衛生管理の方法です。
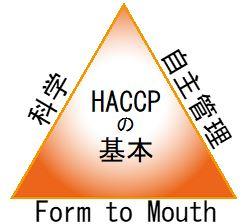 科学とは、ある事柄について考えたり調べたりする時、その方法が同じならば、いつ・どこで・誰であったとしても、同じ答えや結果にたどり着くことで、再現性が必要です。
科学とは、ある事柄について考えたり調べたりする時、その方法が同じならば、いつ・どこで・誰であったとしても、同じ答えや結果にたどり着くことで、再現性が必要です。
食品の衛生管理では、作業する人によって結果がバラバラだったり、同じ人でも毎回違う結果が出てきたりするようなものは、"科学的"ではありません。原因と結果の関係が誰にも分かり易く示されており、エビデンスが明確でなければなりません。
科学的なインスペクションのシステムは、誰が実施しても結果をもう一度再現できる仕組みが絶対条件なのです。
HACCPによる衛生管理の動機付け
HACCPによる衛生管理の主人公は現場で働く従業員の皆さんです。経営者はHACCP導入を決断することです。そのキッカケは「義務化で仕方なく」やバイイングパワーを持つ取引先からの「要請」でもかまいません。
コンサルタントや品質管理担当がHACCPシステムを整備しますが、実際は現場で働いている従業員の皆さんの実践で成り立っています。経営者が現場で働く従業員のHACCP維持活動に感謝をした時、従業員の皆さんに創意工夫の気持ちと智恵が生まれて初めて、成果に結がる礎が出来上がります。
|
■<執筆者プロフィール>
広島惣研株式会社 代表取締役 一般社団法人HACCPと経営 代表理事 光藤 清志(みつふじ きよし)
1970年広島大学水畜産学部食品工学科部卒業その後、食品メーカーに入社し企画営業を学ぶ。
|