-
お問い合わせ
-
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
2024/10/30

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・西村です。
日本では、ここ最近、特に建設業や運輸業を中心に中小企業の倒産が増えてきています。その大きな原因の一つが人手不足です。特に従業員が10名以下の小規模な事業者では、この問題が深刻化しています。この難しい状況を乗り越えるために、AI(人工知能)やロボット技術の活用が今、注目されています。
AIやロボット技術は急速に進化しており、企業の業務効率を大きく改善する可能性を秘めています。しかし、実際に導入するとなると、従業員の給与と技術導入にかかるコストを比較する必要があります。現在、人手不足の影響で、求人倍率が上昇し、賃金も高くなってきています。このような背景があるため、AIやロボットの導入が現実的な選択肢になる企業も増えてきています。
ただし、技術の導入にはタイミングが重要です。あまりにも遅れると、企業の収益がさらに圧迫されてしまい、倒産のリスクが高まります。一方で、適切なタイミングで導入できれば、労働力の不足を補い、業務の効率化や生産性向上を実現できる可能性が広がります。
導入を成功させるためには、企業だけでなく、国や自治体のサポートも必要です。資金的な支援や技術サポートがあることで、中小企業がAIやロボット技術をより導入しやすくなるでしょう。また、企業自身も、従業員のスキルアップや再教育に力を入れることが大切です。
AIやロボット技術は、未来を支える大きな力です。中小企業がこの技術を活用して、成長への道を切り拓けるよう、今後の取り組みが期待されています。
2024/10/23

がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・小林です。
先日、創業者の方から相談がありました。Googleフォトの写真を消しても消えないという内容です。操作説明はすませていたので、操作には問題はないはず。これは...なんでしょう?w
Googleフォトのサービスを使っている人は多かったのではないでしょうか。もともとGoogleフォトは無料で無制限に写真のバックアップができていたので、スマホの写真のバックアップ先として重宝したものです。しかし、保存容量に制限が入り、Googleのストレージが写真でいっぱい⇒Gmailなどのサービスが利用できなくなるという人が多発していました。
さて、今回の相談の詳細は、①ブラウザでGoogleフォトを開き、不要な写真を削除、②スマホのGoogleフォトアプリで状況確認、③スマホのGoogleフォトアプリからは削除したはずの写真が見えている(消えてない)ということです。
分からないので、調べましたw
どうやら、Googleフォトサービス(クラウド)≠Googleフォトアプリ(スマホ)ということみたいですw
Googleフォトのサービスは、クラウド上のGoogleストレージに写真をバックアップするサービスです。ここの写真を削除するところまではOK。
問題はスマホ側のGoogleフォトアプリの挙動です。Googleフォトアプリは、"クラウド上のGoogleフォト内の写真"と"スマホ内の写真"を合わせて表示するアプリだったんです。つまり、クラウド上のGoogleフォト内の写真を消しても、同じ写真がスマホ内に残っている場合、Googleフォトアプリからはその写真が見えてしまうということにw 知らなかった~_(:3 」∠)_
ということで、今回はブラウザからGoogleフォトを開いて、ちゃんとクラウド内の写真が削除できていることを確認しました。知っていれば何ということはないのですが、知らないと慌てますよねw
2024/10/16
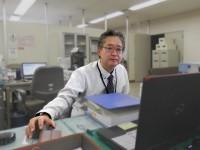 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。
30年以上前に、当時の財団法人広島市産業振興センターにおいて中小企業の方々の支援を担当した時は、インターネットはほとんど普及してなく、支援に必要な情報は、広島市統計書、国勢調査結果報告書、家計調査年報といった「書籍」から収集していました。
支援先の「商圏人口」を算出する場合、①支援先を中心とした一定範囲内の「町丁」を決定し、②この「町丁」の人口を広島市統計書から収集し、③パソコン(当時はワープロ)で表にして「商圏人口」として提供していましたが、②の書籍を一般の方々が入手するには図書館に行くなど手間がかかるものでした。
現在は、インターネット上で国や県、市などの情報が簡単に入手できます。例えば、商圏人口を自らが出すには、①の「町丁」を決定するのは同じですが、②の人口は広島市役所HP(インターネット)で簡単かつエクセルで入手でき、この入手したエクセルを少し加工すれば、すぐに商圏人口が把握できます。
家計調査年報も総務省統計局HPで入手でき、自社(自店)で取り扱っている商品に対する年間支出額等を把握できます。同じく総務省統計局HPで「国勢調査結果」が入手でき、これで商圏内の5歳階級別人口を把握できます。
また、国立社会保障・人口問題研究所が令和5年に「日本の地域別将来推計人口」を出しています。これは、令和2年の国勢調査をもとに令和32年までの5年ごとの30年間についての将来人口を推計したもので、とても衝撃を受けるものですが、今後の経営を考えていく上で一度ご覧いただければと思います。
このように公的機関HPで公開されています情報は、皆様の経営に役立つものが数多くあります。ぜひ、ご活用ください。
2024/10/09

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。
ちょっと前に見たドラマ(20年位前のドラマの再放送)で、写真館の主人A(菅井きん)が、その写真館(自宅付き)の土地・建物を娘Bに譲ろうとして騙される話がありました。Bに譲る際の贈与税を避けるため、次のスキームで引き継ごうとしたのですが、不動産会社Cに騙されたのです。
①Aから、Cにその土地・建物を低額で譲渡する
②譲渡した価格で、BがCから購入する (Cは②の取引を行うつもりはありませんでした)
※顧問税理士(愛川欽也)は、遺言書を作成してBに相続させるようにと勧めたのですが、Aはもう一人の息子が権利証を持ち出して写真館の土地・建物を勝手に売却するのが心配で、直ちにBに譲りたいとの意向でした。顧問税理士も上記の方法について思いついてはいたのですが、「筋が悪い」とつぶやいて黙っていました。
今であれば、このような方法でなくても「相続時精算課税」(以前のブログをご参照ください)の活用も考えられます。ドラマの初回放映時点では「相続時精算課税」は施行前だったのでしょうか。
AからBへ直接贈与した場合には贈与税が発生しますが、このスキームの狙いは、Cを経由して、売買取引としてBに土地・建物を移転させることで、贈与税を回避することなのでしょう。また、AからBへ相場より大幅に安く譲渡した場合には、身内なので低額譲渡(贈与税が発生)と判定される可能性が高いと考え、第三者であるCを間に入れたのでしょうか。Cが信頼できる相手かどうかという話もありますが、このスキーム自体税金対策としてどのようなものでしょうか。
まず、①、②の取引については、もし通常の取引としての実態が伴ってなく、贈与税回避の意図が見え見えだとすると、これらは実質的にAからBへの低額譲渡であるとみなされるかもしれません。①のAからC、②のCからBへの譲渡についても、それぞれ合理的な理由が説明できないと、低額譲渡と判定される可能性は否定できないと思います。
またAに関しては、譲渡所得(所得税が発生)についても考慮する必要があります。
低額譲渡と判定された場合、その取引は時価で行われたとみなされます。売主、買主が個人、法人の違いで、発生する税金の種類、取扱いは次のように変わってきますが、基本的には取引された価格でなく、時価に基づき税金の計算がされることになります。
ア 個人(売主)→個人(買主)の場合
売主:譲渡価格で譲渡所得を計算(この場合は時価での計算はしない)
買主:時価と購入価格の差額分について贈与を受けたとみなされる(贈与税の対象)
なお、取得価格は購入価格等とするが、購入価格が時価の1/2未満の場合には売主の取得価額を引き継ぐ場合あり。
イ 個人(売主)→法人(買主)の場合
売主:時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算
買主:時価で取得したものとする。時価と購入価格の差額は受贈益となる
(同族会社の場合、株式の評価額の上昇に伴い株主に贈与税が発生する場合あり)
ウ 法人(売主)→個人(買主)
売主:時価での譲渡とされ、時価と譲渡価格との差額は寄付金(相手が会社の従業員・役員の場合には給与・役員賞与)となり、損金算入は制限される
買主:時価で取得したものとされ、購入価格との差額は一時所得(又は給与所得)
エ 法人(売主)→法人(買主)
売主:時価での譲渡とされ、時価と譲渡価格との差額は寄付金(損金算入に制限あり)
買主:時価で取得したものとする。時価と購入価格の差額が益金となる
低額譲渡の判定は、譲渡価格が「時価より著しく低い価格」かどうかによりますが、「時価」及び「著しく低い価格」については、一律の基準はなく個々の事情に即して判定することになります。
※所得税に関しては、上記イの売主(個人)に関しては、政令により「時価より著しく低い価格」を時価の1/2未満と定められていますが、その他(ア、ウ、エ及びイの買主)については、法人税や贈与税が課せられる取引なので上記の政令は適用されません。また、ウの買主(所得税が適用)については「時価より著しく低い価格」ではなく、単に「時価より低い価格」とされています(所得税基本通達)。
低額譲渡に関する規定の趣旨は、不当に低い価格の取引による税金逃れを防止することです。通常の取引をされる場合には関係ないとは思いますが、オーナー社長が自分の財産を会社に低額で譲渡するケースは考えられます。このような場合には、思わないところで税金が発生しないよう、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。
当センターでは税理士等の経営の各分野の専門家が皆様のご相談をお受けします。詳細・お申し込みは次のとおりです。
※上記の内容は、令和6年10月1日現在の法令等に基づき記載しています。
2024/10/02

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・久米です。
今年の夏に、スーパーなどの店頭から米がなくなり、商品が出てきても高い値段で販売される状態が続きました。米不足の原因は、昨年の猛暑による不作、外国人旅行者による消費増など、いくつかの要因が重なって起こったようですが、他の食品も値上げが多くなっている状況のなか、買い控えなど消費行動にも大きな影響を与えるものとなっています。今回は、消費行動に大きな影響を与える価格の設定について、どのような方法や考え方があるのかを話していきたいと思います。
最もわかりやすい方法として、その製品をつくるためにかかったコストに一定の利益をプラスする「コストプライス法」があります。この方法だと損失の可能性は少なくなりますが、その製品の需要と供給のバランスや競合する製品の価格などによって、プラスできる利益が大きく影響を受けるものと考えられます。
その他、消費者の心理に着目した価格設定方法として、398円や980円など、あえて端数にすることで安いと感じさせる「端数価格」、高級ブランド品など、あえて高い値段をつけることでステータスを保つ「威光価格」、缶ジュースやペットボトル飲料など、消費者が認識している値段に合わせていく「慣習価格」などがあります。
いずれにしても、消費者の多くは価格の変化に敏感であるため、自社製品の価格を決める際には、さまざまな要素を考慮しながら、バランスの取れた価格にすることが重要であると考えます。