-
お問い合わせ
-
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
2025/03/26
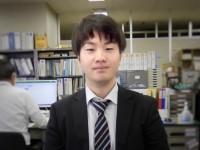
がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・平野です。
近年、働き方改革の推進により、多くの企業で労働時間の短縮が進められています。
しかし、その一方で、「時短ハラスメント(ジタハラ)」という新たな問題が浮上していることをご存知でしょうか?
「時短ハラスメント(ジタハラ)」とは、企業が従業員に対して、業務が終わっていないにもかかわらず、無理やり退社を促すなどの行為を指します。
例えば、
・業務量が減っていないのに、定時退社を強要する
・「残業するな」と強く叱責する
・業務が終わっていない従業員に対して、嫌味を言う
などが挙げられます。
こうした問題は、企業の生産性の低下につながったり、従業員が不利益(残業代が払われない、ストレスによって病気になるなど)を被った場合は企業が責任を問われたりといった結果につながる可能性があり、ハラスメントを受けた本人だけでなく企業にとっての問題となりえます。
そのため企業は、問題の防止のために、労働時間の短縮だけでなく、業務効率化や人員配置の見直しなど、根本的な解決策に取り組む必要があります。
もしも、業務内容の見直し・効率化、人材育成などに関してなどでお悩みでしたら、専門家に無料で相談できる窓口相談などもありますので、ぜひ当センターをご利用ください!
2025/03/19
 おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・阿須賀です。
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・阿須賀です。
当センターの創業支援担当コーディネータに就任して丸7年になりました。就任後に創業チャレンジ・ベンチャー支援事業認定を受けた方はもう少しで100人です。就任前に認定されていた方もあわせると約160人の創業者の事業計画策定やその後の事業展開のお手伝いをしてきたということになります。
最近は、スタートアップだ、ユニコーンだ、ローカルゼブラだ、近年はDAOだ、とかいろいろ新しい言葉も出てきていますが、まだまだ地域に密着した飲食店や美容業、介護や福祉などの業種も多く、それぞれの事業アイデアを形にするお手伝いに走り回っています。
創業手帳や中小企業白書によると、創業5年後の生存率は約8割とのこと。当事業の認定を受けて創業した方は9割以上継続されているので、やはり最初にしっかり事業計画を練ること、新規性独自性オリジナリティや強みをきちんと言語化すること、外部審査員に自分のやりたいことやめざすことを伝えることを経験していただくことは、事業継続の大きな力になっているのかな、と思います。
転出超過の広島において、人手不足の企業さんのことを考えると、独立や創業が増えることはもしかしたら採用難を招いているのかもしれませんが、多様な働き方の時代に人生の選択肢のひとつとして、自分で事業を起こすことを選ぶ方を精一杯応援できれば、と思っています。
広島市で創業をお考えの方、ぜひ創業チャレンジ・ベンチャー支援事業にチャレンジしてみませんか?
2025/03/12
 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・岸野です。
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・岸野です。
現在、「令和7年度見本市等出展助成金(第1回)」の募集を行っていますが、令和6年度から申請手続等に係る変更がありましたので、改めてご紹介します。
変更点
1.申請書類は、持参のみからメール又は郵送、持参もOKです。
2.審査会に出席して商品等のプレゼンが必要でしたが、審査会への出席は不要です。
3.希望者には、受付期間中に、コーディネータによる申請書作成支援が利用できます。
このように、申請手続や審査方法について、申請者の方々の負担軽減につながる見直しを行っています。
対象となる見本市等は、令和7年4月下旬から令和8年3月31日までの間に開催される見本市・展示会等(オンライン見本市を含む。)に出展する事業が対象となります。
令和7年度は、2回の募集を予定していますので、市場開拓にぜひご活用ください。
◇お申し込みなど詳細はこちら
2025/03/05

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・西村です。
AIエージェントの進化が変える中小企業支援の未来
私はこの3年間、中小企業支援に携わり、数多くの経営者と向き合ってきました。現場で強く感じたのは、国内市場の飽和、労働力不足、デジタル化の遅れ、資金調達の難しさといった課題が、ますます深刻化していることです。特に2023年以降、円安や物価高の影響が中小企業の経営を圧迫し、経営環境の厳しさが増しています。
一方で、この3年間でAI技術の進化が中小企業経営に大きな変革をもたらす可能性を強く実感しました。特に2024年以降、AIエージェントの発展が加速しており、AIは単なる情報提供ツールを超え、実際に業務を遂行する自律型エージェントへと進化しています。
AIエージェントが中小企業にもたらす変革
① 事務作業・業務の自動化
中小企業では、人手不足の影響で経営者自身が事務作業や顧客対応を担うケースが多く見られます。しかし、AIエージェントを活用することで、以下のような業務が自動化可能になっています。
・経理・会計処理(AIによる請求書処理や経費精算の自動化)
・営業支援(見込み顧客のリスト作成、メールの自動送信)
・カスタマーサポート(AIチャットボットによる24時間対応)
これにより、経営者や従業員は本業に集中でき、業務効率の向上とコスト削減が可能になります。
② 経営判断のサポート
AIは、単なる自動化ツールではなく、経営者の「参謀」としての役割も果たせるようになっています。
・市場・競合分析(AIが最新の市場動向を収集し、戦略を提案)
・価格設定の最適化(AIが需要予測をもとに最適な価格を算出)
・財務リスク管理(キャッシュフロー分析や融資判断のサポート)
特に生成AIを活用した「AIエージェント」は、経営者と対話しながら意思決定を支援するツールへと進化しています。これにより、データ分析に基づいた精度の高い経営判断が可能になります。
③ 人材不足を補うバーチャルアシスタント
中小企業では、限られた人材リソースの中で多くの業務をこなさなければなりません。AIエージェントを活用すれば、業務の一部をバーチャルアシスタントが担うことが可能です。
・人事・採用業務の自動化(候補者スクリーニング、面接日程の調整)
・マーケティング支援(SNS投稿や広告運用の最適化)
・翻訳・グローバル対応(多言語対応により海外市場の開拓を支援)
例えば、近年登場した長期記憶を持つAIは、企業ごとに最適化されたサポートを提供できるため、人手不足を補いながら企業の成長を支援する役割を果たします。
④ AI導入コストの大幅な低下
かつて、AI導入には高額な費用がかかり、大企業しか活用できないものでした。しかし現在では、オープンソースAIやクラウド型のAIツールの普及により、中小企業でも低コストでAIを活用できる時代が到来しています。
・ノーコード・ローコードの普及(専門知識がなくてもAI導入が可能に)
・クラウドAIの活用(高額な設備投資なしで最新のAIを利用可能)
これにより、中小企業でも大企業並みのデジタル活用が可能になり、競争力を高めるチャンスが広がっています。
中小企業支援の形も変わる
こうしたAIエージェントの普及により、中小企業支援のあり方も大きく変わっていくと考えられます。
・従来の経営相談は、「デジタル化」や「IT導入支援」といった内容が中心でした。しかし、今後は「AI活用を前提とした支援」へとシフトしていくでしょう。
・経営相談の在り方が変化(AIを活用したビジネス戦略支援が主流に)
・中小企業の競争力向上(AIを活かして限られたリソースを最大限活用)
・支援機関の役割の変化(AI活用の橋渡しが重要なミッションに)
中小企業にとって、AIは単なる「コスト削減の手段」ではなく、企業の持ち味を最大限に引き出し、競争力を向上させるための強力なツールとなるはずです。
AIの進化は加速し続けています。今後、AIエージェントは「企業のデジタル社員」として経営を支える存在になり、業務の効率化だけでなく、経営判断や事業戦略にも深く関与するようになるでしょう。
この変革の波に乗るかどうかで、企業の成長スピードが大きく変わります。私自身も、中小企業がAIを活用しやすい環境を整え、持続的な成長を支援することを使命とし、これからの支援活動に取り組んでいきたいと思います。