-
お問い合わせ
-
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
2025/11/26
 おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・阿須賀です。
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・阿須賀です。
日本にシェアリングエコノミー協会ができたのが2015年。今や、消費者庁のサイトにも記載され、すっかり定着しています。
1 空間のシェア
2 モノのシェア
3 スキルのシェア
4 移動のシェア
5 お金のシェア
の中で、創業される方がよく使われているのは、シェアオフィス、シェアサロン、シェアキッチンなどの空間のシェアではないでしょうか。
広島でもここ数年、かなり増えてきています。自宅を公開したくない、登記する住所が必要、という住所のみの利用もありますし、来客やミーティングの場所の確保という場合もあれば、仕事をするため集中できる場所が欲しい、というケースも。中にはドリンク無料のところもあるので、冷暖房完備で自宅よりも快適かもしれません。利用時間も、24時間365日使えるものから、月の上限時間の決まったコースなどニーズによって使い方も様々。郵便ポストや宅配荷物を受け取ってくれるところもあったり、コピー機が共同で使えたり、など自宅よりも仕事しやすい環境が整っているのでは。3Dプリンターやレーザー加工などモノづくりのシェアスペースも増えてきています。
また、菓子製造や総菜・弁当など許認可取得済のキッチンを借りてマルシェなどで販売、や、飲食業許可のあるところでシェアカフェ出店、なども多く見るようになってきました。美容院やエステなどもシェアできるサロンが増えてきています。
これらのサービスは、創業の資金的なハードルを下げてくれるだけでなく、場所のもつ魅力や集客力、という違う価値を活用できるというメリットもあります。さらにそこに集まる事業者同士の交流から新しい価値が生まれる、という視点も見逃せません。
もちろん、消費者にとっても、日替わりでいろいろなお店が楽しめるというのも大きな魅力です。
また、スキルのシェアという視点で、常時雇用ではなく必要な時に必要なスキルをもつ人材を探しやすくなっていますし、副業での創業もしやすくなりました。
さらに、自社で使える物件を持っている場合は、貸会場や貸し駐車場などを登録できるサイトを活用すれば、有休スペースを時間単位で賢くお金に換えることもできたりします。
ということで、創業支援に役立つシェアサービスをコツコツ情報収集していますので、お気軽にお問合せいただければいつでも情報提供します。また、こんなところがあるよ!という情報があったらぜひ教えてください!
2025/11/19
 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・岸野です。
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・岸野です。
先日、「生産性向上に向けたDX支援の進め方」という研修に参加し、中小・小規模事業者の皆さんが抱えている経営・業務課題の整理から最適なITソリューションやアプリの効果的な導入を支援する手法について学んできました。
その中で一つ参考となった、中小企業のデジタル化やIT化をサポートするためのツール「IT戦略ナビwith」を紹介したいと思います。
「IT戦略ナビwith」は、中小機構(中小企業基盤整備機構)が運営するポータルサイトで、今年の4月に「with」という文言が追加され、バージョンアップしたそうです。内容は、簡単な質問に答えるだけで、自社のデジタル化やIT化の状況を把握できる便利なサイトとなっています。
特徴は、回答結果を基に、同業他社と比較した際の自社の立ち位置を「同業他社比較マップ」として可視化でき、IT化の進捗度合いを確認することができることと、自社の経営課題や業務上の問題点をITで解決できるところまでマップで見える化してくれる「IT戦略マップ」も自動で作成され、その解決に役立つ最適なITソリューションまで提案されるところです。
回答時間は、数分で終わりますので、「自社のIT戦略を明確にしたい」「具体的なIT導入に向けた道筋(マップ)を作成したい」とお考えの方は、一度お試しになってはいかがでしょうか 。
【関連サイト】
IT戦略ナビwith
https://digiwith.smrj.go.jp/it-map/
2025/11/12

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・竹内です。
ついこの間まで「暑いですね」と挨拶していたのに、気づけば朝夕はすっかり冷え込むようになりました。
季節の移り変わりの早さに驚くと同時に、今年も残りわずかだと感じます。
カレンダーを見ながら残りの日数を数えると...なんと!50日しかありません( ;∀;)
年末が近づくと、仕事でも私生活でも慌ただしさが増していきます。
私自身、そんな時期こそ少し早めに机の上や書類を整理するようにしています。
積み重ねた書類を見直すと、思いがけず"やり残していたこと"が見つかることもあり、改めて気を引き締めるきっかけになります。
個人事業主の方にとっては、事業年度が1月1日から12月31日までのため、まもなく決算の時期を迎えます。
帳簿の整理など、早めに準備を進めておくと年末を落ち着いて過ごせるかもしれません。
当センターでは、税理士などの専門家にご相談いただける『窓口相談』を実施しています。
経理や決算準備で気になることがあれば、お気軽にご利用ください。
https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/keiei/keiei02.html?kbn=1
2025/11/05
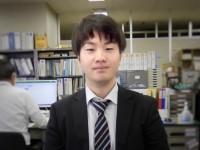
がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・平野です。
今年度(令和7年度)は経営に大きな影響を及ぼす「過去最大の最低賃金引き上げ」が行われ、広島県では時間額65円の引き上げ(1,020円 → 1,085円)が今月1日から適用されています。
皆様対応はお済みでしょうか?もしまだ求人情報の時給が1,085円以下になってしまっていたらすぐに対応しましょう。
過去の引き上げ時も経営に対する影響はとても大きかったかと思いますが、今年度の引き上げは過去最大、影響も過去最大のものになることでしょう。
実際に従業員の賃金がどのくらい変わるのか、最低賃金額で雇用しているものと仮定し、雇用形態別に2つのケースでシミュレーションしました。
週5日、1日8時間勤務のフルタイム従業員(正社員・契約社員など)
月平均労働時間 (8時間 × 5日 × 52週) ÷ 12ヶ月=約173.3時間
基本給の目安 時給 × 月平均労働時間 引き上げ前 176,766円 引き上げ後 188,090円
差額 11,324円/月
➡ 従業員一人当たり月1.1万円以上も上がることになり、複数人雇用している場合はかなりの金額になることが見込まれます。
また、基本給を基礎に、「〇か月分」や「〇を乗じて」などの計算でボーナスを決定している場合はそれも上がることになります。
週3日、1日5時間勤務のパート・アルバイト従業員
月平均労働時間 (5時間 × 3日 × 52週) ÷ 12ヶ月=約65時間
月の給与の目安 時給 × 月平均労働時間 引き上げ前 66,300円 引き上げ後 70,525円
差額 4,225円/月
➡ 従業員一人当たり月4,200円以上も上がることになり、飲食店などアルバイト・パートの方たちでシフトを組んで事業をしている場合、人数も多くなると思いますのでかなりの金額になることが見込まれます。
上記の計算は、前述の通り「最低賃金額で雇用している」場合です。なので、「うちはもともと引き上げ後の最低賃金額よりもまだ高いから影響はなさそう」と感じられる方もいるかもしれません。
ですが、従業員の視点に立ってみると、「世間では過去最大の最低賃金引上げだって言っているのに、私たちは給料が1円も上がらないな・・・」という不満やそれによるモチベーションの低下が発生する可能性が高いです。
なので結果的に、少なくない影響がすべての従業員を雇用している企業に降りかかることになります。
これまでもベースアップ(全従業員の基本給の水準を底上げすること)などに取り組まれてきた企業の経営者にとっては、「また上げなきゃいけないのか・・・」と悩まされることと思います。財務状況が悪化する前に、賃金に対しての対応だけでなく、商品・サービスの価格から経費まで、全体の収支やビジネスモデル自体の見直しをする必要があるかもしれません。
厚生労働省が実施している業務改善助成金やキャリアアップ助成金などの賃金引上げ等に関連する助成金もありますので、この機会に活用してみるのも良いかと思います。
もしも、この度の最低賃金引き上げやそれに伴う事業全体の見直し、助成金の活用に関してお悩みでしたら、専門家に無料で相談できる窓口相談などもありますので、ぜひ当センターをご利用ください。
2025/10/29
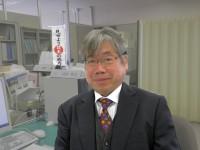 おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。
最近、「GX(グリーントランスフォーメーション)」という言葉を目にしたり耳にしたりする機会が増えました。2025年2月には第7次エネルギー基本計画と「2040年GXビジョン」が示され、脱炭素と経済成長を両立させる取り組みが本格的に動き始めています。
私が2022年に書いたブログ「雪室と風穴」(2022/06/29)では、島根県出雲市の八雲風穴を紹介しました。風穴は山の岩の隙間から冷気が流れ出す天然の"冷蔵庫"です。養蚕業では、蚕の卵を風穴に保管することで、春だけでなく秋まで、連続的に生産することが可能でした。これは自然の冷熱を巧みに活かした"先人のGX"といえます。また、上高地の風穴は富岡製糸所で生糸の安定生産に応用され、明治初期の輸出産業の発展に寄与しました。さらに、道路整備や山岳リゾート開発など、地域経済の変革にも波及しました(2025年10月11日NHK「ブラタモリ」参照)。天然の冷熱資源は、社会全体に影響を与える力を持っていたことが分かります。
その後、電源開発や、冷蔵庫や冷凍室など人工的な冷却技術が普及しました。効率や規模的には優れていましたが、天然のエネルギー資源である風穴の価値は忘れ去られました。しかし今、我々はCO₂排出削減という地球規模の課題に直面し、再び自然と調和したエネルギーのあり方を考える時代に戻っています。
私はGXについて、次のように考えています。
(1)化石燃料の燃焼をできる限り避けること
(2)再生可能エネルギーに加え、地中熱・下水熱・風穴など、身近な天然の熱源を活用すること
・熱のまま直接利用する
・ヒートポンプで熱を汲み出して利用する(若干の外部エネルギーを使用)
地中熱は地下10mで年間を通じて約15℃と安定しています。また、下水道の水温は、夏は外気より5〜10℃低く、冬は外気より5〜15℃高いため、直接熱交換したりヒートパイプで空調に利用したりすることが可能となります。
さらに、広島県にも風穴の可能性を秘めた地形があります。呉市の野呂山や三原市の久井の「岩海」では、蛇紋岩や花崗岩が露出し、岩の隙間に空気が流れる構造をもっています。こうした場所を調査し、霧の発生や冷気・暖気の動きを測定することで、新たな"地熱・風穴資源"の発掘につながるかもしれません。実用化できれば、夏の冷房や冬の暖房、食品加工や地域ブランドづくりなどへの応用も期待できます。
地中に眠る自然エネルギーを見直し、それを地域の新たな価値創造につなげること。こうした視点も、我々が考えるGXの取り組みの参考になると思います。

2025/10/22
 おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・長里です。
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・長里です。
先日、いくつかの国を訪れる機会がありました。
文化や気候はさまざまでしたが、どこに行っても「デザインが日常の買い物やお店選びに自然に影響しているな」と感じました。
みなさんも「パッケージに惹かれて買った」という経験はありませんか?スーパーで飲み物を買おうとしたとき、ついお菓子コーナーに寄ってみたのですが、並んでいた商品のパッケージがどれもおしゃれで思わず見入ってしまいました。色づかいやフォント、余白の取り方などが工夫されていて、気づけば買う予定のはずではなかったお菓子をたくさん買ってしまいました。振り返ると、味や価格だけでなく、"見せ方の工夫"が購買意欲につながっているんだなと感じました。
また、旅の途中で立ち寄ったカフェも印象に残っています。特別有名なお店ではありませんが、なんとなく「いいな」と感じて、入ってみました。古い建物を改装したお店で、緑の庭と開放感のある空間が印象的でした。1階には、店内で作られた陶器や食器が並んでおり、2階のバルコニー席では自然光が差し込み、落ち着いた雰囲気の中でコーヒーを楽しめました。木の家具や陶器、緑の植物がうまく調和していて、空間全体に独特の居心地の良さがありました。思い返すと、お店を選んだ理由は、味や価格よりも"お店の雰囲気"に惹かれたからだと思います。
こうした体験から、デザインや空間の演出は、単なる見た目の工夫ではなく、お客さまに「つい手に取ってみたくなる」「ふらっと立ち寄りたくなる」と思ってもらうための大切な要素だと改めて感じました。商品のラベルやチラシの表現を見直す、SNSでの伝え方を工夫する、店内のレイアウトを少し変えてみる。そんな小さな取り組みでも、販路拡大やファンづくりにつながるのではないでしょうか。
広島市では、「いい店ひろしま」という表彰制度があり、店舗演出や接客、ユニバーサルデザイン対応などに優れた小売店を選定しています。受賞店舗を見ていると、お客さまが過ごしやすいように考えられた工夫が随所に感じられます。そうした積み重ねが、「また来たい」と思ってもらえる理由になっているのだと思います。9月からは受賞店舗のおすすめ商品やイベント情報等をいい店ひろしま公式Instagramで紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
【公式】いい店ひろしまインスタグラム(@iimise_hiroshima_official)
当センターでは、店舗演出やチラシ作成、SNS発信など、日々の販促に関する相談を受け付けています。「何から始めたらいいのか分からない」という方は、広島市産業振興センターの窓口までお気軽にご相談ください。
2025/10/15
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・倉本です。
当センターでは平成18年度から令和4年度において、基本的な商業機能が優秀と認められ、地域に根付き親しまれている小売店舗を「いい店ひろしま」として顕彰する事業を実施してきました。
その受賞店舗を紹介する【公式】いい店ひろしまインスタグラム(@iimise_hiroshima_official) では今、受賞店舗の商品やイベントをご紹介しています。
「こんなの探していた!」と思えるイベントも発見できるかもしれません。ぜひアクセスしてみてください!
フォロワー登録もお待ちしています。
2025/10/08
 おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北浦です。
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北浦です。
今回、AI(CopilotとGemini合作)を使って「脳とAIの比較」の文章と図を作成してみました。AIの高速な情報処理で文章を作成し、それに対して相応しい「意味」を持つ言葉を付与する作業を通じて、AIと共創するプロセスを実感することができました。
----- 以下、AIと共同制作による文章 -----
脳とAIの比較
AIは、人工ニューロンを規則的な層構造で接続し、同期的な並列処理を行うことで、膨大な情報を高速に処理します。現在主流の「特化型AI(Narrow AI)」は、特定のタスクにおいて人間を凌駕する性能を発揮しますが、以下のような限界も抱えています。
・「身体性・感情の欠如」
人間のような感覚フィードバックがないため、意味や価値判断の生成が困難です。
・「統計的処理への依存」
情報の関連性を数理的に捉えることはできても、文脈や意味を自律的に理解する力には限界があります。
・「学習の柔軟性」
脳のように学習によって接続を動的に変化させる柔軟性(可塑性)や、ひらめきのような非同期的な情報伝達は再現が難しい。
将来的には、AGI(汎用人工知能)やASI(超知能)の登場が予測されており、経営判断・戦略立案など、企業活動の根幹に影響を与える可能性があります。しかし、これらのAIが人間のような「質的飛躍」を遂げるには、非線形な統合能力や意味生成のメカニズムを獲得する必要があります。
人間の脳の非線形性と創造性の源泉
一方、人間の脳は、1000億以上のニューロンが非線形かつ動的に接続され、視覚・聴覚・運動・感情などの情報を並列分散的に処理します。特筆すべきは、脳が単純な入力と出力の比例関係ではなく、学習や経験の蓄積によって、臨界点を超えた瞬間に突然統合や覚醒が起こるという非線形的な性質を持っていることです。
これは、量的な蓄積が質的な飛躍へと転換する瞬間であり、直感・創造・ひらめきといった「知性の発露」が生まれる源泉です。
長年の経験から一瞬で最適な判断を下すベテラン職人の技や、試行錯誤の末に突然ひらめく画期的なアイデアは、まさにこの非線形な知性の表れと言えるでしょう。
このように、人が究めて極めた職人技や、ひらめき・直感には、AIは当分の間追いつけません。
Google ai studioで作成した「AIと人間の創造的共存」の図 経営に求められる新たな視点
経営に求められる新たな視点
脳とAIは、それぞれ異なる強みを持っています。AIは効率性と再現性に優れ、人間の脳は統合・適応・創造において比類なき力を発揮します。
未来の競争優位は、AIの効率性を活用しつつ、人間の創造性と統合力を最大限に引き出す意思決定にかかっています。経営者にとって重要なのは、AIを単なるツールとして位置づけ、異なる背景や価値観を持つ人々が集まることで生まれる、新しい解釈やひらめきといった「意味生成能力」を中核に据えることです。
----- 以上、AIと共同制作による文章 -----
2025/10/01
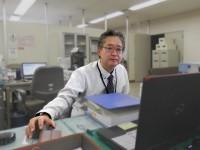 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。
私が初めて「クルマ」を所有したのは、40年近く前で、兄と一緒にディラーに行って、軽自動車を『49万8千円』で購入しました。その時は、外観、内装、メーカーなどは関係なく、安く買えて安く維持できる、この点だけで購入したと記憶しています。現在、同じ車種・同等グレードの車を購入しようとした場合、40年近く前の2倍以上の価格となっているようです。
一方、現在の初任給は、ざっと比較しても40年近く前の初任給に対して2倍以上になっていませんが、乗用車の新車販売台数は、1985年の310万台に対して、2023年は399万台と3割程度増加しています。今回は、収入の伸び以上に価格が高くなっている「クルマ」の販売台数がなぜ伸びているのか、思いつくまま記述してみます。
40年近く前に「クルマ」を所有するということは、購入することしか思いつきませんでしたが、現在は、様々なカーリースがあり、カーシェアリングもあります。消費者の「クルマの所有」に対する消費行動は、購入以外の方法も選択肢として取り入れられ、これに対応した『商品』も提供されてきています。
ここ数年、物価の上昇を生活の中で実感するとともに、高額な商品やサービスの動きが鈍ってきたという声を耳にします。生活必需品と言える「クルマ」でも、消費行動に合わせた商品の提供にも舵を切り、販売を維持・増加させています。小売業、サービス業を営む経営者の方々も、消費者が購入(利用)しやすい商品の提供を模索して、笑顔と共に実践していただきたいと思います。
この記事を書いている2025年9月に、某自動車会社の「〇〇ーR]という車が生産終了となりました。生産終了の理由の一つに、運転支援システムなどの現在の車に求められている要件への対応があるとされています。どんなにファンが多い商品であっても、時代の変化に対応していく必要があると感じさせられる出来事です。
2025/09/24
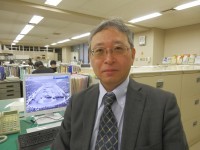
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・姫野です。
近年、Webサイト(ホームページ)を持つ事業者が増えています。事業内容や所在地などをインターネット上で確認できることから、Webサイトは事業活動において欠かせない広報媒体と言えるでしょう。
SNSで代用されるケースもありますが、Webサイトは「公式サイト」としての信頼性が高く、SNSと連携することで集客効果をさらに高めることが可能です。
さて、皆様はWebサイトの制作や運用をどのように行っていますか。おそらく、多くの方が制作会社など外部の事業者に委託されているのではないでしょうか。
近年は定型化(テンプレート)や自動化(自動でインストール)が進み、ある程度の知識があれば自作も可能になってきましたが、それでも専門的な知識やスキルおよびセンスが必要な場面は多く、依然としてハードルは高いと言えます。
Webサイトを公開するには、まずレンタルサーバー(以下「サーバー」)を契約し、ドメイン(インターネット上の住所のようなもの)を取得します。そのうえで、表示する文言や画像などのコンテンツを制作し、Webページとして構築。これをサーバーにアップロードし、必要な設定を行うことで、初めてブラウザ上で閲覧できるようになります。
しかし、Webサイト制作を外部に委託する際には、契約・運用・技術・法務など、さまざまな面でリスクが潜んでいることは意外と知られていません。特に注意すべきは、契約や権利関係にまつわるリスクです。
さあ、Webサイトを作ろう!と意気込んで、委託業者とはサイトの内容と費用の話しばかりをして肝心な契約内容がおざなりになった結果として、たとえば、以下のようなトラブル事例があります。
- 著作権が制作会社に帰属しており、改変や再利用ができず、他のサーバーへ移転できない
- ドメインやサーバーが制作会社名義で契約されており、移管を拒否されたり高額な費用を請求された
- 契約書が存在せず、納期・費用・修正範囲などで認識の違いが生じた
- 著作権侵害の可能性がある素材を使用しており、改変や再利用ができない
- ライセンス違反の素材(画像・フォントなど)を使用していて、第三者から訴えられた
- 品質やセキュリティの問題が放置され、Webサイトが乗っ取られたり情報漏えいが発生した
このような事態を防ぐためには、どうすればよいのでしょうか。
まず、制作会社とは必ず契約を締結してください。口約束での依頼は避けましょう。契約前には、特に以下の点を確認することが重要です。
■サーバー・ドメインの帰属に関する注意点
- サーバー契約者の名義が自社か制作会社かを確認する
- サーバーの管理権限(FTP、CMS、メール設定など)が誰にあるかを明確にする
- ドメインの契約者名義(Whois情報)を確認し、自社名義であるかを確認する
- サーバー費用の支払い主体(自社か委託先か)を把握する
- サーバー移管の可否と手続き方法を事前に確認する
- 障害対応や保守体制の有無と範囲を確認する
- ドメインの管理権限(DNS設定、更新など)が誰にあるかを明確にする
- ドメインの更新費用の支払い主体を確認する
- ドメイン移管の可否と手続き方法を確認する
- ドメイン失効時のリスクと対応策を共有しておく
- 契約書や覚書に、サーバー・ドメインの所有権が自社にあることを明記する
- 委託終了後も自社で継続利用できることを契約上保証する
- 管理情報(ID・パスワード)の引き渡し条件を明確にする
- トラブル時の対応責任と連絡体制を事前に合意しておく
■著作権・素材の取り扱い
- 使用する画像・イラスト・動画・音源などの権利関係を事前に確認する
- 制作物(デザイン、文章、プログラムなど)の著作権が誰に帰属するかを契約書で明記する
- フォントや写真などの素材が商用利用可能か、ライセンス条件を確認する
- 外部提供素材(ストックフォト、テンプレートなど)の使用範囲や再利用可否を把握する
- 制作会社が独自に用意した素材の出所とライセンスを確認する
- 著作権侵害が発生した場合の責任の所在を明確にしておく
- 納品後に自社で使用・改変・再利用する際の制限があるか確認する
- クレジット表記や著作権表示が必要な素材が含まれているかを確認する
盛りだくさんの内容ですが、これらはほんの一部です。契約書にこれらの事項がきちんと明記されているかどうかを必ず確認したうえで、契約してください。
本来、サーバーやドメインは依頼者側(自社)に権利があるべきものですが、契約内容によっては制作会社側に権利があると主張されるケースもあります。
場合によっては、サーバー上のコンテンツやプログラムを修正する必要が生じることもありますが、契約内容が不明確なまま手を加えると、「勝手に改変した」としてクレームや費用請求につながる可能性があり、非常に危険です。
状況によっては、正直なところ、一から作り直した方が早くて確実な場合もあります。
「安かったから」「親切そうだったから」「知人の紹介だったから」・・・その結果、費用も信頼も失ってしまうことのないよう、慎重に進めましょう。
万が一トラブルに巻き込まれた場合は、当センターの窓口相談で弁護士相談などをご活用ください。