-
お問い合わせ
-
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
2025/07/30
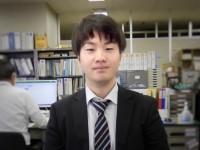
がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・平野です。
2025年4月、育児・介護休業法が改正され、4か月近く経ちました。皆様対応はお済みでしょうか?
この度の改正への対応は単なる義務ではなく、労働法遵守の観点からも、人材確保・定着の観点からも、中小企業の皆さまが向き合うべき重要なテーマです。
少子高齢化が進み、人手不足が深刻化する中で、企業が従業員のライフイベントに寄り添い、安心して働き続けられる環境を提供することは、持続的な企業成長に不可欠です。
まず、今回の法改正に対応をするメリットについてご紹介したいと思います。
優秀な人材の獲得と定着:
育児・介護との両立支援の充実は、「働きやすい会社」としての魅力を高めます。これは、人材の流出を防ぎ、新たな人材を惹きつける大きな武器となり、労働市場での競争力向上に直結します。
従業員のモチベーション向上と生産性アップ:
安心して育児や介護と仕事を両立できる環境は、従業員のエンゲージメントを高め、生産性向上にも寄与します。精神的な負担が軽減されることで、業務への集中力も増し、結果として企業の業績に良い影響をもたらします。
労働トラブルの未然防止とリスク回避:
法改正への適切な対応は、労働基準法や育児・介護休業法といった労働法の遵守にもつながります。これにより、従業員との間で発生しうる休業や休暇、勤務形態に関するトラブルを未然に防ぎ、予期せぬ損害賠償リスクや社会的信用の失墜といった経営リスクを回避することができます。労働基準監督署からの指導や勧告を避けるためにも、法改正への理解と対応は必要です。
企業のブランドイメージ向上:
法律を遵守し、従業員を大切にする企業姿勢は、顧客や取引先、そして社会全体からの信頼獲得に繋がります。これは、企業の持続的な成長を支える重要な要素となります。
次に、改正の主なポイントと留意点を紹介します。
今回の法改正では、主に以下の点が変更・拡充されます。
<子の看護等休暇の対象拡大>
旧:子の看護休暇 → 新:子の看護等休暇
対象:小学校就学前の子を養育する労働者
変更点:感染症に伴う学級閉鎖、入園・入学式なども取得事由に追加。
留意点:労働者がこれらの事由で休暇を請求した場合、使用者は原則として拒否できません。
拒否した場合は、育児・介護休業法違反となる可能性があります。
<所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大>
対象:小学校就学前の子を持つ労働者まで拡大。
留意点:対象労働者からの請求があれば、原則として残業を命じることはできません。
違反した場合、厚生労働大臣による助言、指導、勧告のほか、請求者への不利益な扱い(解雇や降格、減給を行うなど)
があると、企業名公表の対象になるリスクも伴います。
<短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加>
3歳未満の子を養育する労働者への短時間勤務制度の代替措置として、テレワークが追加。
留意点:テレワーク導入にあたっては、労働時間管理や労働安全衛生、通信費負担など、労働基準法や労働契約法に関する
新たな課題が生じます。これらを明確にした規程整備が求められます。
<介護のためのテレワーク導入の努力義務化>
留意点:努力義務ではありますが、従業員が必要としているのに導入を検討しない場合は、
企業イメージの低下や人材流出に繋がる可能性があります。
<育児休業取得状況の公表義務の拡大>
改正前は従業員1,000人超の企業に公表義務がありましたが、改正後は従業員数300人超の企業にも義務付けられました。
留意点: 公表を怠った場合、行政指導の対象となる可能性があります。
改正に対応するための取り組みとしては以下のようなものがあげられます。
就業規則・社内規程の総点検と改定:
育児・介護休業に関する規程はもちろん、労働時間、休暇、テレワークに関する規程が、改正法に適合しているか確認し、速やかに改定しましょう。
従業員への周知徹底と啓発:
法改正の内容や、新たな制度について、従業員に分かりやすく説明し、疑問点を解消しましょう。従業員が自身の権利を理解し、制度を利用しやすい環境を整えることが、トラブル防止に繋がります。
社内説明会の実施や、社内掲示物、イントラネットでの情報公開なども有効です。
柔軟な働き方の検討と導入(規程整備含む):
テレワークやフレックスタイム制、短時間勤務など、従業員が育児・介護と仕事を両立しやすい働き方を積極的に検討しましょう。導入する際は、労働時間管理、費用負担、評価制度など、労働法上の論点をクリアにした明確な規程を定めることが重要です。
相談窓口の設置・周知とハラスメント対策:
育児・介護に関する相談を受け付ける窓口を設置し、従業員が気軽に相談できる環境を整えましょう。また、育児・介護休業の取得を理由とした不利益取扱いや、ハラスメント(前回紹介した時短ハラスメントなど)は、育児・介護休業法で禁止されています。
助成金制度の活用検討:
育児・介護と仕事の両立支援に関する助成金制度もあります。これらを活用することで、法改正への対応コストを軽減できる場合があります。
法改正への対応は、単なる義務ではなく、労働法を遵守し、企業価値を高めるための戦略的投資です。適切に対応していくことで従業員にとって働きやすい、「選ばれる企業」へと進化していきましょう。
もしも、この度の法改正への対応に関してお悩みでしたら、専門家に無料で相談できる窓口相談などもありますので、ぜひ当センターをご利用ください!