-
お問い合わせ
-
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
2009/08/31
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・常本です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・常本です。
今回は、特別金融相談窓口の利用案内をします。
リーマンショック以降、国際的な金融危機となっている現状で、資金繰りに苦慮しておられる中小企業の経営者の方も多いと思います。
資金繰りといっても、ただお金を借りるだけでは、今後の経営状況が回復するとは限りません。
そこで、資金繰りの対応策や企業の将来的な方向性について、総合的に相談できる「特別金融窓口相談」を中小企業支援センターで行っています。
資金繰りに重点を置いた窓口相談で、主に税理士を相談員としてアドバイスを行っています。
個別の中小企業で、税理士などを雇っていない方には特にお勧めです。一回の相談時間は50分ですが、複数回利用しても料金はかかりません。
経営の現状を打破するヒントを相談の中から見つけてはどうでしょうか。
2009/08/28
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャー免出です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャー免出です。
石油が、飛鳥時代に越後より燃える水・燃える土として献上されたという記録があります。その石油は、江戸時代は、「くそうず」として知られ、灯りとして、また防腐剤・薬剤としても使用されていたということです。
しかし、その石油は、燃やすと真っ黒な煙と嫌な臭いを出すために、積極的に活用されてきませんでした。近年になり、石油を精製して灯油・ガソリン等にすることによって、急速に照明・燃料として使用されることになり、石油の時代が到来しました。20世紀は、石油の時代となりました。
現在、石油ピークの論議もおき、先行きが心配され始めています。また昨年は、石油価格が大幅に高騰するという事態も生じました。そして何よりも地球温暖化への懸念があります。日本は、その石油をほぼ100%輸入に頼っています。1973年のオイルショック前は、日本はエネルギー供給の77%を石油に依存していました。現在は、それが50%以下になっています。
低炭素社会への取り組みと、エネルギー自給率の改善(現在4%の自給率-原子力発電を除く)を図るために、石油等の化石燃料だけでなく、太陽光発電・バイオ燃料・風力発電等のエネルギーの多様化が求められています。その中で、中小企業の皆様にとってどのようなビジネスチャンスが生まれてくるのか、またどのような取り組みが必要となるのかを今後考えていきたいと思います。
2009/08/27
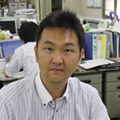 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・平山です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・平山です。
広島市では、9月18日まで、新分野進出支援融資(特別資金)・創業支援融資(特別資金)を募集しています。
これは、通常1.4%の金利であるところを、1.0%の低金利でご融資するというものです。
条件として、当センターにて実施する事業可能性評価委員会にて事業計画が優れているという評価を受ける必要があります。また、別に金融機関および信用保証協会の審査もあります。
皆さんが抱いているビジネスプランに対して、専門家の客観的な評価を受けることができ、認められればその上で低利融資を受けることが出来るという制度です。ぜひチャレンジしてみてください!
2009/08/26
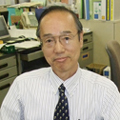 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャー・近藤です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャー・近藤です。
これまで、さまざまなグローバルビジネスに必須なコミュニケションツールを紹介しましたが、他にも各種のニーズに合わせた多様なツールがあるようです。
このうちいくつかは語学力が必要ですが、語学力がなくとも可能な方法もありますので、活用してみましょう。
私は、他社との共同商品開発、マーケティング等の領域でいわゆるグローバルビジネスに携わってきました。そのとき、基本となるのは海外企業とのコミュニケーションであり、その中でいろいろなツールを使ってきました。
その頃を振り返りながらEメール編、会議編と話しを進めてきたわけです。あと残っているのは、外国人とのFace-to-Faceのミーティングやパーティ、ディナー等でのコミュニケーションということになります。ミーティングに関しては、これまで会議編で述べてきたことと変わることはないでしょう。
問題は、そう、仕事から離れた時のコミュニケーションです。
私が海外駐在中、長く駐在をしてきた諸先輩からよく聞いた話は、ヨコ飯(本当は洋食の意味のようですが、外国人との食事の意味で使っていました)はどうにも厄介なものだということです。
どんなに海外生活に慣れても、生まれ育った文化や、食生活の違いは如何ともし難いものです。余程慣れた友達になっても、このヨコ飯が長く続くと、耐えられません。
国によって、食事の際のしきたりや、マナー、そして独特なスピーチの仕方等もあり、まさに学ぶより慣れろというのが結論ではないでしょうか。
さてそれでは、このあたりで長々と続いたグローバルビジネスにとってのコミュニケーションツールのお話のお開きとさせていただきます。長いおつきあいありがとうございました。
2009/08/25
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・岸野です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・岸野です。
隔年で行われている、コンピュータ&ネットワークEXPO'09広島が11月に開催されます。
今回のEXPOでは、デジタル情報活用の普及とともに想定される様々な最先端技術やビジネスモデルの紹介のほか、日本のインターネットの父 村井 純氏(慶応義塾大学環境情報学部教授)の基調講演『インターネットの新しい潮流(仮題)』が予定されています。
また、世界最大級のインターネット技術に関する国際会議『第76回IETF広島会議』も同時期に開催され、会期中はインターネット、ネットワーク技術に関わる技術者やベンダー企業の方々が多数、広島市を訪れます。
----------------------------------------
コンピュータ&ネットワークEXPO'09広島 ~入場無料~
◆開催日 平成21年11月11日(水)~13日(金)
◆会 場 広島県立産業会館西展示館(展示・セミナー)
広島県健康福祉センター(講演会・セミナー)
※詳細は、「こちら」をご覧ください。
◆問い合わせ先
コンピュータ&ネットワークEXPO'09広島 事務局
電話 082-242-7408
----------------------------------------
2009/08/24
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャー・浜田文男です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャー・浜田文男です。
「中小企業が元気になるための経済産業省が進める施策J-SaaS」の研修会が全国で開催されます。現在、15の研修会が予定されています。
ここ広島でも開催されます。講師はJ-SaaS操作指導員が行い、実際にパソコンを使用します。まずは研修受講(無料)を申し込んでいただき、会員登録(無料)を行い実際に体験してみることをお勧めします。
さて、J-SaaSのサービスメニューを見てみますと、現在12のカテゴリーで31のサービスが提供されています。概要は下記になります。数字はサービス数です。
①財務会計 8 ②経理 2 ③給与計算 4
④税務申告 2 ⑤グループウエア 3 ⑥経営分析 1
⑦セキュリティ対策 2 ⑧販売管理 2 ⑨プロジェクト管理 2
⑩インターネットバンキング 2 ⑪社会保険手続き 2 ⑫顧客商談管理 1
(詳しくは、 J-SaaSサービス一覧 を参照ください。)
今後も、J-SaaSの新たな動きや情報を紹介する予定です。
2009/08/21
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する広島市中小企業支援センターの経営革新担当・佐伯です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する広島市中小企業支援センターの経営革新担当・佐伯です。
7/31で今年度の「いい店ひろしま」の募集が終了しましたが、たくさんの表彰候補店舗を推薦していただき、有難うございました。
現在、表彰候補店舗を審査する消費者審査員を下記のとおり募集しています。まだ定員まで若干の余裕がありますので、是非ご応募ください。
■応募資格
1. 20歳以上(平成21年9月1日現在)で、市内に居住されている方
2. 原則、居住区内にある審査対象店舗を訪問し、店舗の評価をしていただける方
■募集人員
40名程度(応募者多数の場合は、居住地区等を踏まえて選考します。)
■業務内容
審査対象店舗の評価(審査対象店舗を訪問し、簡単な採点表による評価を行うものです。)
※ 消費者の視点から審査していただきますので、必ずしも専門的な知識は必要ありません。
■謝礼等
謝礼金はありませんが、交通費の補助として、3,000円のバスカードを支給します。
■応募方法
応募申込書に必要事項を記入のうえ、下記応募先へ郵送又はFAXしてください。
【申込書配布場所】
広島市役所、各区役所、各区民文化センター、広島商工会議所、広島市中小企業支援センターなど
応募申込書はこちらからダウンロードできます。
■募集期間:平成21年8月1日(土)~8月31日(月)17時15分必着
2009/08/20
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネジメント担当・竹田です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネジメント担当・竹田です。
昨年9月15日のリーマン・ブラザーズの破綻を契機とした金融危機・世界同時不況による国内外の販売不振や円高の影響により、国内企業の業績は急激に悪化し、企業経営にとって大変厳しいものとご推察申し上げます。
このため、当財団では、広島市内の中小企業の経営動向、当面する課題及び中小企業支援センター事業への要望などを調査することで、広島市内の中小企業の経営実態を的確に把握し、今後の事業へ反映させるため、センター職員が皆様方企業へ直接伺わせていただき、ヒアリング調査を実施させていただいております。
8月中の調査を予定しており、既に調査にご協力いただいた企業の皆様には、お忙しい中、大変ありがとうございました。また、これから調査に協力いただく企業の皆様には、本調査の趣旨をご理解いただき、ご多忙中のところ誠に恐縮ではございますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
2009/08/19
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当 北林昌樹です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当 北林昌樹です。
最近、「創業を考えているのだがどのような手順で進めたら良いか」「創業するためにはどのような届け出が必要か」「事業計画を作ったが、採算がとれるだろうか」など、創業についての相談を良く受けます。
これらの相談については、当支援センターの窓口相談(無料)にお申し込みいただいて、中小企業診断士等の専門家からアドバイスを受けることも有効ですが、それとともに、お勧めなのが、中小企業庁が発行している「夢を実現する創業」という小冊子です。
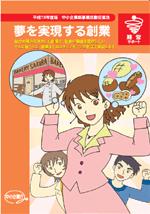 この小冊子には、創業を目指す方を対象に、「創業に向けてのチェック事項」、「創業時に必要な届出書類」、「事業計画書の作り方」など、創業する際に必要な基本的事項が、わかりやすく説明されています。
この小冊子には、創業を目指す方を対象に、「創業に向けてのチェック事項」、「創業時に必要な届出書類」、「事業計画書の作り方」など、創業する際に必要な基本的事項が、わかりやすく説明されています。
専門家のアドバイスやセミナーを受ける前に、この小冊子を一読されていると、理解が一層と深まると思いますので、創業をお考えの方は、是非参考にして下さい。
なお、「夢を実現する創業」は、下記のURLをクリックすると、無料でご覧になることもできますし、印刷も可能となっています。
「夢を実現する創業」http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/manyual_sogyo/19fy/download/manyual_sougyou.pdf
2009/08/18
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・小林です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・小林です。
財団法人広島市産業振興センターと広島市では、次の助成金・融資制度の2回目の募集を行っていますので、お知らせします。
1.平成21年度環境関連製品・技術開発助成金(2回目)
2.平成21年度広島市先端科学技術研究開発資金融資(2回目)
■受付期限 平成21年8月31日(月) 17時15分までに必着
■問い合わせ先 財団法人広島市産業振興センター
中小企業支援センター 担当:小林、常本
TEL:082-278-8032 FAX:082-278-8570
その他、環境関連製品・技術開発助成金、広島市先端科学技術研究開発資金融資に関してご不明な点があれば、お気軽に経営革新担当・小林、常本までご連絡ください。
2009/08/17
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・新本です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・新本です。
この研修は、市内でこれから創業しようとする方、または事業をはじめて間もない市内中小企業者の方を対象にして、創業に必要な知識・手法の講義、実習、演習などを3つのコース(ホップ・ステップ・ジャンプ)に分けて実施します。
・ホップコース(募集中)
内容:創業手続き・事業プラン作成・資金繰り・マーケティング手法の解説、コミュニケーショントレーニン
グ
日時:平成21年9月19日(土)、9月26日(土)、10月3日(土)、10月12日(祝・月)の10:00~
17:00。全4回
場所:広島市立中央図書館 セミナー室(広島市中区基町3番1号)
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
・ステップコース(平成21年9月15日募集開始予定)
内容:販売体験に基づく顧客ニーズのつかみ方や事業プラン作成の実務演習
日時:平成21年11月7日(土)、11月15日(日)、11月22日(日)、11月28日(土)の10:00~
17:00。全4回
場所:広島市産業振興センター1階 研修室(西区草津新町1丁目21番35号)ほか
・ジャンプコースは別途ご案内
市内でこれから創業しようとする方、または事業をはじめて間もない市内中小企業者の方、この研修会に参加してみませんか?きっと皆様の役立つ情報・知識が得られると思います。
2009/08/14
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営担当マネージャー・景山です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営担当マネージャー・景山です。
「ひろしまベンチャー助成金」は、平成14年度にスタートし、15年度以降は(財)ひろしまベンチャー育成基金の事業として年2回の助成を行い、今回で13回目を迎えます。
12回までに、801先(一般枠のみ)の応募があり、うち111先(同)に対し合計119,500千円の助成金を交付し、広島県のベンチャー支援制度として定着してきました。
第11回までの助成先の状況をみると、残念ながらベンチャーの宿命で事業断念となった先もあるものの、約70%の先は、事業化進展、販路開拓、立ち上げのいずれかの事業化段階に至っており、相応の成果を挙げています。
例年通り、6月・7月に募集がありましたが、今回は、昨秋以降の景況悪化の影響もあるのか、法人37先、個人30先、計67先と、4年ぶりに60先を超える多数の応募がありました。事業分野別では、情報通信が最も多く、次いで新製造技術と今回「エコ特別賞」が創設された環境分野が続いています。
8月下旬に一次審査を終え、9月中旬に二次審査(面接)を行い、10月下旬には助成金贈呈先が決定される予定です。
どんな先が「大賞」に選ばれるのか、初回「エコ特別賞」はどうなるのか、注目頂きたいと思う次第です。
2009/08/13
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・馬上です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・馬上です。
先日、NHKの番組「たったひとりの反乱」で、男性社会の中でも困難に立ち向かいながら会社を立ち上げた女性起業家の物語を放映していました。
昭和40年代、高度経済成長の階段を登り始めたころ、世はまさに男性社会。女性が会社を興すことなどほとんどなかった時代に、女性ならではの生活者の視点で、当時、普及し始めた電話を利用した子育て相談「赤ちゃん110番」という事業を立ち上げました。
ところが、読みはズバリ当たり相談は殺到しましたが、お金を回収する方法を考えていなかったため苦境に立たされます。おまけに、電話回線がパンクし、当時の電電公社に呼び出され、お叱りを受けるはめに。そのときの電電公社の幹部役の江守 徹のセリフが印象的でした。(細かい言い回しは多少違ったかもしれませんが)
「情熱とアイデアだけでは事業はできん。お金がもらえる仕組みを考えなさい」
私も、これまで女性の起業支援に携わり、女性・シニア創業パッケージ型支援事業では起業をお考えの方の事業計画をいろいろと見させていただきましたが、まさにこの部分が弱い計画が多かったように感じられます。
ただ、情熱とアイデアはご本人次第ですが、「お金がもらえる仕組み」は他の人に聞くこともできます。
当センターの窓口相談などをご利用いただき、専門家の意見も聞きながら、お金が儲かる事業計画をお立てください。
2009/08/12
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のプロジェクトマネージャー・久保です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のプロジェクトマネージャー・久保です。
(7月号からの続き)
前号までで「発想」の段階ではどういう作業をするのかを学びました。
ここで、これまでのおさらいをしてみましょう。
1.商品の開発は基本に忠実に、そして地道に、着実に進めること。
2.ターゲットとなる、お客様像をはっきりさせること。
3.お客様はこれから開発しようとする商品を、どんな使い方をするのかを考えること。
4.そしてお客様が期待する使い方を実現するためには、その商品はどういう機能を持っていなければな
らないのかを考え商品コンセプト(=商品像)を描くことです。
この段階で開発しようとする商品の"機能的目標"が決まったことになります。
そして最後に大事なことは、営業・企画・設計・製造等この商品開発に携わる全ての関係者がこの「機能的目標」を共有し、さらに、開発途中で変更が必要になった時には関係者の合意の上で変更することです。
決して一部の人間だけで変更を決めてしまったり、変更があったことを関係者が知らないという状況を作ってはならないということです。
さてそれでは次号で、いよいよ設計の段階に進みましょう。(次号に続く)
2009/08/11
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北林幹生です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北林幹生です。
先日、中小企業庁が取りまとめた「平成20年中小企業実態基本調査報告書」を見ました。この調査は平成19年度決算に基づく実績報告をもとに、平成20年8月1日に実施したというものです。
このため、昨秋以降の輸出、生産等の急激な減少実態までは反映されていないようですが、それでも例えば中小企業の1企業当りの売上高を見ると、全体で対前年調査比0.5%増(19年調査は3.7%増)にとどまっていました。次回の調査では、アメリカ発の金融危機の影響が色濃く反映された結果が出るものと思われます。
中小企業がこの厳しい状況を乗り切り、業績を向上させるには、経営手法の見直しなどの取組みが必要です。そこで、このたび中小企業の経営者等の皆様を対象に、広島市立中央図書館、地域力連携拠点ひろしま診断協会(中小企業診断協会広島県支部)と共催で「ガンバル中小企業応援セミナー」を開催します。
製造業のコストダウン、小売・サービス業の経営革新、IT、資金調達など様々なテーマを取り上げて、経営課題を解決するための手法についてのセミナーと個別相談会を6回に分けて行います。
セミナー講師は地元広島で活躍中の中小企業診断士などをお招きしており、また個別相談会も当日の講師や中小企業診断士が対応いたします。ご関心のあるテーマであればいずれの回でも参加(参加費:無料)できます。
各テーマ、申込方法などは こちら をご覧ください。
2009/08/10
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する広島市中小企業支援センター所長の藤田です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する広島市中小企業支援センター所長の藤田です。
今年の梅雨は、平年より約2週間遅く6月9日頃に梅雨入りしました。前半は雨が少ない日が続きましたが、7月に入ってから本格的な雨模様となり、特に7月後半の豪雨は記憶に新しいところです。
被害に遭われた方々に心からお見舞いを申しあげます。
さて、梅雨が長引くことで気温が上がらず、エアコンや夏物衣料の売上が低迷しているほか、農業でも低温による生育不良の兆候が伝えられるなど、気候の変動が、停滞する経済に一層の悪影響を与えないか心配されます。
これから、梅雨が明けると本格的な夏が訪れます。夏といえば「夏祭り」。各地の商店街では、景気低迷を吹き飛ばすべく「夏祭り」にあわせたセールやイベントに知恵を絞り、経営者の皆さんや地域のボランティアの方が汗を流しておられます。一度、各地の商店街の"夏イベント"に出かけられてはどうでしょうか。
本市では、広島市の産業内に、「ひろしまの商店街」を設け、イベントなど商店街の情報を発信しています。
市内商店街の皆様、このサイトへの掲載は無料です。また、自商店街のホームページへのリンクも張れます。このサイトを情報発信にご利用ください。
お問い合わせは、広島市中小企業支援センター創業支援担当までお気軽にしてください。
電話:082-278-8880 E-mail:assist@ipc.city.hiroshima.jp
2009/08/07
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャー・免出です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャー・免出です。
日本の今年の環境標語が「低炭素社会」です。低炭素社会とは何かと思い、古い手持ちの広辞苑を開いてみました。しかし、出て来ません。これはやはりつい最近出てきた言葉に違いありません。そこでインターネットでその意味を探ってみたところ以下が出てきました。
「地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を、現状の産業構造やライフスタイルを変えることで低く抑えた社会。化石燃料使用量の削減、高効率エネルギーの開発、エネルギー消費の削減、資源の有効利用などによって実現を目指す」
これを3つにまとめますと、
1.エネルギーとして化石燃料からの脱却を図りつつ新エネルギー開発に取り組む。
2.省エネ装置の開発、輸送装置の燃費向上、住宅の断熱性向上等が必要である。
3.森林等でCO2を吸収しつつ、二百年住宅のように資源を粗末に扱わない。
現在、環境の悪化が、至る所で見られるようになりました。土壌汚染、海洋汚染、酸性雨や黄砂、集中豪雨や土砂くずれ、砂漠化、熱帯雨林の消滅・森林の荒廃化、ごみの大幅な増加等々、いずれも簡単には対処できない問題です。さてどうするかといわれても、全体のシステム・ライフスタイルが変わらなければどうしようもありません。しかも厄介なのは、これが日本だけで対処してもどうにもならないことです。
世界の人々と共同でこの問題に取り組んでいくことが求められているものと思います。
2009/08/05
 おはようございます。
おはようございます。
がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の副所長の土佐です。
先日、あるセミナーにいき、中小零細商店(飲食、サービス業を含む)の経営に役立ちそうな情報がありましたので紹介します。
まず、繁盛しているお店は、資本力などよりも「口コミと紹介」で集客しているということ。大々的な広告をうつよりも、口コミが有効です。そのためには、中小零細商店は「いいものだから買って下さい」という自己中心的な発想が必要となります。口コミは、店側からも発信できます。人がいて、商品・サービスがあり、ストーリーがあれば十分。どの店にもストーリーはあります。そうすると、人は人に教えたくなるものです。
次に、常連客が来なくなった理由を調査したところ、最も高い理由は、「なんとなく忘れていた」という単純なものです。この対応策は、DMを打つこと。商品紹介をしなくても「ご機嫌いかがですか」といった簡単な挨拶でいいのです。年4回こうしたDMをうてれば、企業の倒産率は驚くほど低下するといわれていました。
なお、飲食店では、テーブルごとにあるメニューを席数分用意すると売上高が、1.3倍になるという話もありました。 参考までに。
2009/08/04
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・常本です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・常本です。
前回は、窓口相談の効果的な利用方法について書きましたが、今回は「中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定」いわゆる「セーフティネット認定」の申請について書きます。
セーフティネット認定は、国(中小企業庁)の指定する「業況の悪化している業種」に該当し、かつ直近3か月の平均売上高等が前年同期と比べて3%以上減少している場合等に広島市長名で不況業種認定をするもので、通常の融資とは別枠で広島県信用保証協会の保証付の融資の申込みができるものです。
昨今の不況を反映してか、申請件数は多く、通常は申請から5日~1週間程度(土日祝は除く)の期間で認定になりますが、毎月の月末には、月半ばまでと比べても倍近い申請件数になる日があります。そのため、認定に通常以上の時間が必要になる場合があります。
ところが最近、月末近くに、「月末までに認定していただきたい。」という申し出が特に多くなっています。
認定を早く受けたいのはどの企業も一緒です。「至急」等の申し出があったからといって先に申請書の確認作業ができる保証はありません。運転資金の確保は、企業経営の根幹にも関わることですので、融資が必要になることが明らかなときには、早めに金融機関、信用保証協会と融資の実行について協議して、余裕を持って認定申請をしていただきますようお願いいたします。
2009/08/03
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する広島市中小企業支援センターの経営革新担当・佐伯です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する広島市中小企業支援センターの経営革新担当・佐伯です。
店舗演出、接客などが優れている「いい店ひろしま」の選定に消費者の意見を反映させるため、消費者審査員を募集します。
■応募資格
(1) 20歳以上(平成21年9月1日現在)で、市内に居住されている方
(2) 原則、居住区内にある審査対象店舗を訪問し、店舗の評価をしていただける方
■募集人員
40名程度(応募者多数の場合は、居住地区等を踏まえて選考します。)
※ 店舗の応募状況により変動します。
■業務内容
審査対象店舗の評価(審査対象店舗を訪問し、簡単な採点表による評価を行うものです。)
※ 消費者の視点から審査していただきますので、必ずしも専門的な知識は必要ありません。
※ 10店舗程度を考えていますが、店舗の応募状況により変動します。
■謝礼等
謝礼金はありませんが、交通費の補助として、3,000円のバスカードを支給します。
■応募方法
応募申込書に必要事項を記入のうえ、下記応募先へ郵送又はFAXしてください。
【申込書配布場所】
広島市役所、各区役所、各区民文化センター、広島商工会議所、広島市中小企業支援センターなど
応募申込書は https://cms.assist.ipc.city.hiroshima.jp/iimise/ からダウンロードできます。
■募集期間:平成21年8月1日(土)~8月31日(月)17時15分必着