-
お問い合わせ
-
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
2010/09/30
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のプロジェクトマネージャー・久保です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のプロジェクトマネージャー・久保です。
「突貫工事」という言葉があります。
「仕事量が多く困難な工事を、文字通り死に物狂いになって短期間で仕上げる」の意ですが、工事に限らず日常の仕事においてもよく使われる言葉です。その時の張り詰めた緊張感、必死に仕事にとり組む姿は、傍で見ている人には一種の頼もしさを感じ、また当事者としても終わった後の達成感・充実感に、すがすがしさを感じることさえあります。
しかしプロジェクトの管理という観点からこれを見てみると、決して褒められたことではないのです。なぜか?それはこの「突貫工事」というのは「通常でない仕事のやり方を予想に反して強いられる」ということで、人・物・金が工期優先という基準で投じられることになるため、単位仕事量当たりの原価が高くなるからです。また急場の混乱は尋常ではなく更なる不測の事態を招くリスクも高まります。
確かに現実のプロジェクトの運営では予測もできない事態が起こることを「ゼロ」にはできませんが、全体計画立案時点で考え得る限りの事態を想定すること、日々の業務の進捗管理をキチット行うことでかなりの部分、事前に察知することができこれによって回避処置をあらかじめ講ずることも可能になります。
「突貫工事」に追い込まれ無理なスケジュールで切り抜けることは「手柄話」でもなんでもなく、むしろプロジェクト責任者のマネージメント能力が不足している結果だと真摯に受け止めなければなりません。
2010/09/29
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・常本☆康之です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・常本☆康之です。
今回は、中小企業支援センターの事業のうち「特別金融相談窓口」について紹介します。
相談会場は、中小企業支援センター相談室(西区草津新町一丁目ミクシスビル)ですので、当センターに来ていただく必要はあるのですが、銀行出身の中小企業診断士や社会保険労務士、税理士などの実務的な資格を持つ専門家が相談員なので、この経済危機を原因として発生した資金繰りの悪化、資金調達、経費削減などの相談に特化して対応するものです。
1回の相談時間は、50分と決まっていますが、何度利用しても無料なので、複数回利用して課題を解決することも可能なのです。
例えば、銀行への追加融資を依頼する場合の注意点や返済プランの作成、キャッシュフォローの見直し、事業承継で発生する税金などへの対策、事業廃止する場合の清算方法など現実に直面している課題への具体的な解決策の提案などを行っています。
この不況下で、資金問題の解決に向けたアドバイスをもらいたいという方は、ぜひご利用ください。
特別金融相談窓口の日程など詳細は、こちらからどうぞ。
2010/09/28
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・新本です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・新本です。
11月開催の研修会をご紹介します。
この研修会では、利益を生み出す生産現場を築くためのコストダウン手法を身につけていただきます。
◆日 時 平成22年11月11日(木) 13:30~16:30(3時間)
◆会 場 広島市まちづくり市民交流プラザ 北棟5階 研修室C
(広島市中区袋町6-36)
◆対 象 広島市内の中小製造業の経営者、管理者、現場監督者など
◆受講料 1,000円
◆定 員 30名(先着順)
◆カリキュラム
(1)生産現場を取り巻く環境と課題
(2)現場改善の必要性、コストダウン活動の必要性
(3)現場改善によるコストダウン
ア ムダやロスの見つけ方
イ 工程作業改善のポイント
ウ レイアウト改善のポイント
(4)ものづくりに関する意識改革
◆講 師 株式会社アイピック 代表取締役 青井 宏安
詳しくはこちらをご覧ください。
2010/09/27
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する広島市中小企業支援センター所長の藤田です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する広島市中小企業支援センター所長の藤田です。
今日は、「六日の菖蒲(あやめ)十日の菊」(むいかのあやめ、とおかのきく)という諺をご紹介します。意味は、時期に遅れたものは、役に立たないことのたとえです。
五月五日の端午の節句に用いる菖蒲(あやめ)は六日では間に合わないし、九月九日の重陽の節句に用いる菊も十日では役に立ちません。
ビジネスでは、「QCD(キューシーディー)」(Q:品質、C:コスト、D:納期)の3つを兼ね備えることが大切です。そのうちQとC、即ち、「いいものを安く(適正な価格で)」供給しても、D、即ち、「必要な時に必要なものタイミングよく」供給できなければ、大切なビジネスチャンスを逃してしまいます。
当センターでは、中小企業の皆様の「QCD(キューシーディー)」の向上のために専門家やマネージャーを派遣しています。お気軽に、ご相談ください。
2010/09/24
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北林です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北林です。
最近、街を歩くと、庭先の植木の葉が茶色く枯れている痛々しい姿をよく見かけます。今夏の猛暑を如実に物語る風景のようです。
さて、当支援センターの事業の一つに、女性・シニア創業パッケージ型支援事業があります。この事業の認定を受けられた方の1人である小田百合さんは、和装着物を洋服や小物にリメイクする事業を行っています。創業から2年半が過ぎ、常連のお客様がたびたび来店されるそうで、中には、東京在住の女性の方もおられるとのこと。
その小田さんが、10月1日から15日まで、「絹の手仕事展」と題して、絹の着物生地からリメイクした洋服や小物の新作をギャラリーで展示します。これまで以上にお客様に喜んでいただけるものをお届けしたいという次のステップのために、芸術的な試みとして、実用向きでありながら、美しく、遠くから眺めてみたくなるような作品をつくり、展示することにしたのです。
先日、中区上八丁堀のお店を訪問したところ、ブラウス、スカート、ワンピース、子供服など洋服を50点、バッグ、ポーチ、日傘など小物を100点展示することをお聞きしました。来店されたお客様の中には、出展用の洋服が気に入って、是非にと請われ、お売りしたこともあるそうです。
10月の涼しい風の中、是非、小田さんの作品を見ていただきたいと思います。
なお、そのギャラリーですが、こちらも女性・シニア創業パッケージ型支援事業の認定(平成20年度)を受けられた船本由利子さんが運営しています。
小田さんのお店「ぐれいす ぱんせ」
所在地:広島市中区上八丁堀5-5-105
電話:082-222-0108
船本さんのお店「Gallery+Cafe カモメのばぁばぁ」
所在地:広島市西区横川町一丁目5-23
電話:082-232-5074
URL:http://kamomenobaabaa.web.fc2.com/
2010/09/22
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・岸野です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・岸野です。
中小企業支援センターでは、起業に関心のある方や起業後間もない中小企業の経営者を対象に、起業者の経営上のレベルアップとビジネスマッチング、起業予定者の起業意欲の向上、参加者間の人的ネットワークの形成を図っていただく場として①基調講演、②パネルディスカッション、③情報交換会で構成する「起業家フォーラム」を開催いたします。
基調講演では、株式会社スプラム 代表取締役 竹内幸次氏をお招きし、起業することの意義や起業の厳しさ、夢を実現し事業経営を行う喜びなど、講師ご自身の起業体験をお話いただく予定です。
10月1日(金)より受講者の募集を行いますので、ふるってご参加ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
日 時:平成22年11月23日(祝・火)14:00~18:30
場 所:広島YMCA 2号館 コンベンションホール
内 容:①基調講演
②パネルディスカッション
③情報交換会
定 員:50名(先着順)
受講料:①②無料、③参加費3,000円
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2010/09/21
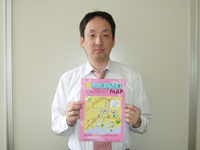 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・佐伯です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・佐伯です。
今回は、平成21年度「いい店ひろしま」受賞店舗の楽々屋草津店さんについて、自分が実際に行って、感じたことを紹介します。
楽々屋草津店さんは、西区草津南の宮島街道沿いにある店舗で、様々な介護用品を扱っていますが、中でも、シルバーカーと高齢者用の靴は、特に豊富な品揃えを誇っています。
店員さんも、1つ1つの商品の性能や違いを分かりやすく丁寧に教えてくれ、高齢者にとって、非常に分かりやすい手書きのPOPが商品毎に置いてあります。
また、お店をコミュニティの場とするため、店長さんが、毎月、健脳体操教室やフラワー教室などを企画しています。
是非、皆さんもお店を訪れてみてください。
(店舗外観)
 (店舗内装)
(店舗内装)
2010/09/17
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の佐伯です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の佐伯です。
さて、前回は、保証協会へ債務がなくても、連帯保証人が完済した場合には、主たる債務者(借り受け人)が連帯保証人へ返済が終了していなければ保証は受けられないというお話をしましたが、今回は、事例というよりは、一般的にこんな状態にある場合には、保証承諾は得られないというケースについて、簡単に説明したいと思います。
保証協会との取引におけるケースです。
(1) 保証協会が代位弁済を行って企業で、協会に求償債務が残っている場合
これは、企業が金融機関から保証付きで融資を受けたが、途中で返済できなくなり、保証協会が
企業に変わり金融機関に残りの借入金を返済し、企業(借受人)が未だ保証協会に対して肩代わり
してもらった借金を返済していない状態にある場合です。
(2) 保証付きの融資を受けたが、返済が滞っている場合
上記(1)の場合は、いわゆる「事故」扱いとなっている状態ですが、この(2)場合は、 「延滞」の扱
いになっている場合を指していいます。遅れながらでも返済している場合や1回あたりの返済額を減
額している場合などがあたります。
このような状態になっている場合は、新たな保証は出来ないという意味です。
(3) 設備資金として保証付きの融資を受けたが、その設備を導入していない場合
これは、資金使途(借入金の使いみち)が保証の際の条件と異なっているため、新たな保証はで
きないということを意味しています。通常、設備資金は、新たな価値を生み出す、或いは生産の効率
を高めるといった前向きな資金使途と考えられていますが、そのことを逆手にとって、実際には借入
金の返済などといった一時しのぎのために使ったのではないかということになり、信用ができないと
いうことを意味しています。前回の「与信」に通じる考え方ですね。
(4) その他、保証枠を超えており、追加の担保提供ができない場合など
これは、無担保の限度額を超える場合や企業の業績から判断される保証限度を超えるような場
合で、それを補う担保の提供ができない場合を指しています。
いろいろなケースがありますね。
ここで取り上げたケースは、基本的な事項を説明していますので、「わが社の場合はどうかな?」と思われる場合は保証協会にご相談されることをお勧めします。
さて、次回は、金融取引等において保証協会を利用できないケースについて、説明したいと思います。
2010/09/16
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャー免出です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャー免出です。
以前は、私達の普通の感覚では、飲み水をボトルで買って飲むという発想はなかったように思います。しかしそれがごく普通のことになってきました。
私が、米国に滞在していたのは、1980年代ですが、その当時飲み水を買って食事を支度していました。というのは、水道水を使うと硬水のため、体内に石が蓄積するということを恐れたためです。味噌汁を飲んだ後に、お椀に白いものが残るということもありました。またフランスにいた1975年当時も、水の代わりにワインを飲むと云われており、水を買って飲んでいたように思います。
つまり、欧米では、飲み水を買って飲むということは普通ですが、日本では当時あまり考えられないことでした。しかし、現在は、美味しいアルプス産の水とか、カナダ産の水をとても手軽に手に入れることが可能になりました。
一方、CFP(カーボン フット プリント)から考えるとどうなるのかという議論が現在なされつつあります。地球環境に考慮したCFPを考えると、地産地消が理想的です。何故ならば、輸送にかかるエネルギーがとても少なく、CFPを小さくできるからです。 先日講演会で聞いたところでは、CFPの次に、米国は新たにWFP(ウォーター フット プリント)を検討し始めているということです。
食糧を作るのに、水が必要です。牛丼一杯で水が2000リットル必要です。牛肉を輸入するということは、水を輸入する事だよということです。食料を大量に輸入している日本は、世界最大の水輸入国になるとのことです。水の豊富にある日本が、水の輸入国であったという言い方は驚きです。
さて私達はどう考えるべきでしょうか。今水不足の問題がクローズアップされつつあります。WHOの水基準でいくと、世界では11億人が水の安全性に問題があるといわれています。また米国では、地下水が枯渇して来つつあり、早晩大きな問題になるともいわれ始めました。
水は、石油についで大きな関心事になって来ていると言えるのではないでしょうか。そんな時に、食糧も含めて水を輸入し続けることが、どれだけ可能か、一方、CFPをどう考えるべきか、地産地消も含めて、検討して行かなければならないときが来つつあるのではないかと思われます。
2010/09/15
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・下縄です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・下縄です。
高橋 克彦著の「火怨(ひえん)」は吉川英治文学賞の受賞作ですので、多くの方が読まれていると思いますが、中小企業の経営戦略の策定の参考となりますので、紹介させていただきます。
辺境の地と蔑(さげす)まれ、それゆえに朝廷の興味から遠ざけられ、平和に暮らしていた陸奥の民。八世紀、黄金を求めて支配せんとする朝廷の大軍に、蝦夷の若きリーダー・阿弓流為(あてるい)とその仲間たちは遊撃戦を開始します。
朝廷軍との圧倒的兵力の差から夜襲で朝廷軍に打撃を与えますが、朝廷軍も体制を整え3万の軍で攻め入ってきます。阿弓流為(あてるい)たちは、地形や天候を考慮し、相手の立場となって3万の軍を有して攻めるなら、どこをどのように通って攻めてくるかの検討を重ね、結論を導き出します。その上で、どこを、いつ、どのように攻めれば、少ない将兵でも効果的な打撃を与えることができるかを検討し、実行していきました。
当初は兵力の差で、蝦夷軍を簡単に征服できると相手を甘くみていた朝廷軍は、策もなく力で押したため、阿弓流為(あてるい)たちの策にまんまとひっかかり、大敗を喫します。また、敗因を中央政府に天候のせいにするなど、嘘の報告を上げるため、有効な打開策がないまま兵力だけをつぎ込むため、20数年にも及ぶ戦いとなりました。
この間、阿弓流為(あてるい)たちは、朝廷軍の戦いの中で、武器として何が有効で、兵力の不足は騎馬隊で補うとともに、人材育成に努め、戦う集団へと着々と準備を進めていきます。
こうした戦略が実際の企業経営の中で、多いに参考となりますので、まだ、読まれていない方は、是非、読んでいただき、既に、読まれた方も今度はじっくりと読んでいただければ、幸いです。
創業に関する様々な問題や課題について、ご気軽に創業支援担当・下縄までご連絡ください。
2010/09/14
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・中宮です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・中宮です。
前回、「考え方を変えてみる」ということで、「時々立ち止まって、第3者の視点から、客観的に自分たちの仕事を見つめなおしてみてはいかがでしょうか」と書きましたが、今回はその具体的な方法についてご提案したいと思います。
まず、仕事を見つめなおすとはどういうことなのか考えてみたいと思います。皆様、長い間ずっと同じやり方で仕事を続けていることはないでしょうか。また、他の部門のことを考えず、自分の部門のことだけを考えて仕事をされていることはないでしょうか。
長年同じ仕事のやり方を続けていると、知らない間にその方法が唯一の方法だと思い込んでしまい、新たな方法があるかもしれないという発想すら浮かばなくなってしまいます。また、自部門のことだけを考えてしまうと、他部門との連携が疎かになり、企業全体としての利益を損なう恐れも発生します。
このようなことから考えると、仕事を見つめなおすとは、企業という組織の中における、自分たちが担っている業務(役割)を洗い出すことで、自部門の問題点を探し出し、それを他部門のスタッフと共有することで、企業全体の問題点を浮かび上がらせて、それを改善することで、企業の業績の向上・業務の効率化を図ることだといえるかもしれません。
次に、業務の洗い出しの方法について、ひとつの方法を提案したいと思います。上記のとおり、業務の洗い出しは、他部門と問題点を共有する必要があるので、専門用語等の使用は避けて、誰でも分かる簡単なものであることが重要です。案として、ある一つの業務をその作業工程ごとに分解し、その作業手順を紙のカードに書き出していくことをお勧めします。この作業手順は、細かければ細かいほど、問題点が見つかりやすいと思います。そして、それぞれの業務について、作業手順のカードをすべて作成したら、それらを業務ごとに、壁などに張り付け、全員で手順の確認を行ってみてください。そうすると同じ作業を別の工程でも行っている「ダブり」や必要な作業がなされていないなどの「漏れ」が発見できると思います。
こういった作業を、自部門だけでなく、他部門も巻き込んで行うことで、企業全体で無駄がなくなり、業務の効率化、延いては業績の向上につながるかもしれません。是非一度取り組んでみられてはいかがでしょうか。
2010/09/13
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の常本☆康之です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の常本☆康之です。
今回は、中小企業支援センターの事業のうち「一般窓口相談」について紹介します。
一般窓口相談の会場は、中小企業支援センター相談室(西区草津新町一丁目ミクシスビル)で行うため、会場に来ていただく必要はありますが、中小企業診断士などの資格を持つ専門家が相談員なので、経営に関する悩みや経営革新計画の作成、新商品開発、販売促進、人材育成、ネット通販など、様々な内容の相談に対応できます。
1回の相談時間は、50分と決まっていますが、何度利用しても無料なので、複数回利用して課題を解決することも可能なのです。
50分では相談しきれないとお考えの方、複数回利用することも前提に相談してみませんか。また、複数回利用するといっても同じ課題でないといけないということはありません。最初に、全般的なこと、2回目に販路拡大について、3回目に労務・人事についてなど内容を発展させながら相談を受けることができるのです。
この不況下で、経費削減をしながら経営アドバイスをもらいたいという方は、ぜひご利用ください。
窓口相談の日程など詳細は、こちらから
2010/09/10
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・小林です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・小林です。
今回はパソコンの管理事例についてご紹介します。
先日、職場の共有フォルダのバックアップ作業をしていましたが、画像ファイルのバックアップ時間の長いこと。(´Д⊂グスン
これは、私の「画像ファイルは大きい」という思い込みによるものなのか、実際に長いのか?実際に長いとすれば、どれくらい長いのか・・・よくわかりません。
これは、共有フォルダの中のファイル構成を把握する必要がありそうです。今回は、このあたりを調べてみることにします。何か面白いことが分かるかもしれません。
まずは、ネットでドライブのファイル構成を表示してくれるソフトを探します。うまい具合にフリーのソフトがありましたので、早速、ファイル構成を見てみます。
我々が普段、よく使っているワード、エクセルのファイルは、ファイル数では全体の65%を占めているが、ファイルサイズでは全体の25%程度しかないこと。
画像ファイルのファイル数は全体の16%しかないが、ファイルサイズでは全体の36%を占めており、サイズシェアでトップとなっていること。
ワード、エクセルの平均ファイルサイズは0.2MBであるが、画像ファイルの平均サイズは1MB、音声ファイルの平均サイズは65MB、動画ファイルの平均サイズは218MBであること。中には1.5GBを超える動画ファイルがあること。
毎年、10GB程度のデータが増えており、ワード、エクセルファイルは2,200程度が生成されていることが分かりました。(これは面白い!と思うのは私だけ?)
このようなデータを持っていると、設備導入時のマシンスペック積算などに使えそうですね。
いい勉強させていただきました。
2010/09/09
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の佐伯です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の佐伯です。
前回からずいぶん間が空いてしまい、申し訳ありません。
さて、前回は、滑り込みセーフといった感じで、何とか保証承諾が得られたケースのお話をしましたが、今回は、保証承諾が受けられず、結果として融資を受けることができなかった事例についてお話したいと思います。
(事例)
A氏が相談に来られた時のことです。
「新しく事業を始めようと思います。ついてはその開業資金を賄うため、融資を受けたいのですが。」という内容でした。いろいろとお話を聞いているうちに、以前、事業をしておられましたが、残念ながら取引先の倒産で連鎖倒産となり、今回が再出発とのことでした。
倒産されたときには、保証付きの融資を受けておられましたが、その借入金の負債については連帯保証人の方が完済しているとのお話でした。
負債は完済しているので一見、何も問題ないように思えますが、実は、この話には裏があり、A氏は、倒産した際に、所在不明の状態となり、結果として連帯保証人の方に残債の返済を押し付けた形となっていたのです。
保証協会では、連帯保証人が完済した場合であっても、その後において、主たる債務者(A氏)が連帯保証人の負担した額を連帯保証人に返済したという事実が明らかにならない限り、A氏に対する保証は行なわないのです。
私は、A氏にこの話をし、確認したところ、連帯保証人への返済はしておられませんでした。当然、A氏はがっかりされておられましたが、みなさんはこの事例をどのようにご覧になりますか。
確かに保証協会に対するA氏の債務は無くなっているのですが、それはA氏が苦労されて返済されたものではない、ということが最も問題視されているということです。
つまり、借りたら返すという義務を果していない人、信頼できる人か?ということになります。
保証することを「与信」と表現する場合があります。信用というものが事業活動をする上で、いかに重要かを示した事例ではないかと思います。
次回も保証が受けられなかったケースのPartⅡをご紹介したいと思います。
2010/09/08
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャーの浜田文男です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャーの浜田文男です。
先日、ある方からのメールマガジンを拝見していましたら掲記の記事が目に留まりました。引用しますと『実は、この「エネルギー検定」は、今年の6月始まったばかりの検定なんです!お得なことに、受験料は0円。つまりタダなんです!いつでも好きなときに、インターネットで30問の設問を30分以内で回答するだけ!正解率80%以上で合格証書も発行されます。「初級」編と「中級」編があります。まずは,お試しに初級編をチャレンジしてみてはいかがでしょうか?』(http://www.ene-kentei.jp/)
そこで、早速、初級編に挑戦しました。アレ???合格しません。何回か挑戦してやっと合格しました。合格証を出力して、ホッとした次第です。問題は勘で答えられますが、重要なことは、その根拠を調べることです。
さらに、「エネルギー検定の目的は、エネルギーに関する正しい基本的な知識を持ち、社会の中で率先してエネルギー問題、環境問題に取り組む"人"を育成することです。」ということですので、今後とも自らの育成を図りたいと思います。
2010/09/07
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・馬上です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・馬上です。
私もこの歳ですから、健康管理のために毎年人間ドックを受けていますが、今年初めて「便に血が混じっていますから、大腸内視鏡検査を受けてください」と言われ、先日検査を受けました。
以前、うちの母親も受けて、とても痛かったと言っていたし、お尻からボールペン位の太さの内視鏡を入れると思うと、結果よりも検査自体が不安でした。
当日は朝から2リットルの水(腸の洗浄液)を10分~15分おきに2時間かけて飲み、その都度トイレに行き、洗浄液がそのまま便となって出るまでそれを続けます。
午後になってからが、いよいよ本番の検査です。最初は「んっ」としましたが、意外にもスムーズに入り、先生もなぜか「早い、早い」と言っていました。内視鏡の画像をディスプレイに写しながらいろいろと説明してくれて、思ったよりも早く済んでホッとしました。
結局、検査結果は「異常なし」で安心しましたが、検査の後が大変でした。腸を膨らませるために内視鏡からガスが出るのですが、そのために腹がパンパンになり、家に帰ってガス(おなら)が出るまでが、普通に歩くのも難しいほどでした。
当センターでは、企業の健康管理のため、人間ドックならぬ企業ドック診断を行っています。財務分析や工場の稼働分析、商店の商圏分析など総合的に企業の健康状態を調査・分析し、異常(問題点)があれば改善案を提示(処方)します。
中小企業の社長さん。ご自分の健康も大事ですけど、企業の健康も大事です。この機会に企業ドック診断を受けてみませんか。
2010/09/06
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する広島市中小企業支援センター所長の藤田です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する広島市中小企業支援センター所長の藤田です。
私は、学生時代に剣道をしていました。そのときの師範の永田侃先生が、剣を志すものの心構えとして良くおっしゃっておられた「守破離(しゅはり)」という言葉をご紹介します。
「守破離(しゅはり)」とは、武道や芸事を修行する際の心構えを説いたものです。
「守」とは、師匠の言うことをひたすら守り実行すること。即ち、基本を覚えること。
「破」とは、その上で、自分の独自の工夫を加えること。
「離」とは、自分の流派をつくること。
この守破離の考え方は、ビジネスや日常業務にも応用できます。
師匠を先輩や上司(または先人が残した業績)と置き換えてください。
仕事をする上で、まず、先輩や上司の指示や教え、以前実施した仕事のやり方を基本にして同じようにやってみることが大切で、その次に、そのやり方、方法に、自分流の工夫や研究を加えて、さらに良い仕事に仕上げること、これが、ビジネスでの守破離です。
ただ、「守」ばかりでは単なる前例踏襲で何の進歩もありませんし、むしろ、やってはならないことです。「守」の延長の「破」(=革新)が重要であり、さらに、それを続けることで、その先に「離」(=独自のスタイル)の確立があります。
このことを、東レ経営研究所社長の佐々木常夫さんは「プアなイノベーション」より「優れたイミテーション※」と言われています。実に、うまい表現で的を射た仕事術だと思います。
当センターでは、中小企業の皆様の「破」(=経営革新)を応援しています。是非、ご利用ください。
※ 「部下を定時に帰す仕事術」(WAVE出版)
2010/09/03
 おはようございます。
おはようございます。
がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北林です。
アフリカ諸国において女性起業家育成支援を行っている行政機関等の担当職員を対象とした研修が広島県内を中心に行われ、8月18日に広島市における起業家支援事業を説明する講師を務めました。
この研修は、(財)ひろしま国際センターが国際協力の一環として、(独)国際協力機構(JICA)から「アフリカ地域女性起業家育成支援」コースを受託して行われたもので、そのカリキュラムの一部として当支援センターで実施している起業支援事業(起業支援アドバイザー派遣、女性・シニア創業パッケージ型支援、女性起業家サポート、創業者向けセミナー・研修会など)を説明しました。
事業ごとに説明し、質疑応答を行ったところ、どの事業にも様々な質問を受けました。特に、女性・シニア創業パッケージ型支援事業について関心を持たれ、事業計画書の作成に当たっての支援方法、事業PR方法、融資の仕組みなど、自国で事業を実施する場合を想定して詳細な内容の質問を受けるとともに、追加資料の要求もいただきました。
女性起業家育成支援のための実践的な事業の情報を収集したいという思いを強く感じました。


2010/09/02
 おはようございます。
おはようございます。
がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のプロジェクトマネージャー・久保です。
今やIT 化の時代です。
大半の職場で、各人の机にはコンピューターの端末機が置かれていることと思います。
これに伴って日常の業務連絡は電子メールで行われるようになりました。同じ部屋に居る同僚に電子メールでメモを送ることも珍しくありませんし、会議用の資料なども事前にメールで配布し、当日は各人がプリントアウトしたものを持ち寄ることをルール化している会社もあります。
電子メールでは、連絡内容を打ち込んで発信先を指定して送れば、自動署名の機能を使わなくても送信者のアドレスを見ることで誰が送信してきたものかは予測がつきますしまた、受発信日も自動的に記録されるのでずいぶんと便利になりました。
しかしあまりこれに慣れすぎると、きちっとした資料が作れなくなる危険性があるので注意が必要です。
以下は実際にあった例ですが、ある会社の社内会議に出た時にその会議で配られた大半の資料に作成者の名前、作成日が記入されていませんでした。また表題のない資料もいくつかありました。
業務用の書類には公式のものから、個人の備忘録までいろいろなものがありますが、少人数とはいえ複数人が集まって行われる会議で使用する資料であれば最低限の体裁は整えたいものです。
たとえば会議の議事録であれば表題、作成者の氏名、作成日、決定事項、継続審議となった事項については誰がいつまでにどういう対応を取るのか等は最低限記されている必要があります。
これはビジネスをする上での基本ですが、常日頃から訓練しておかないとなかなか身につかないことです。
本人の努力もさることながら、上司としても気がついた時には指摘をするよう、日ごろから課題意識を持っている必要があるでしょう。
2010/09/01
 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・新本です。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・新本です。
先日、「キャッシュフロー経営と利益・資金計画策定支援」研修を受講しました。
この研修会では、キャッシュフロー経営と利益・資金計画策定支援について、決算書(貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(C/F))などを利用して、中小企業の経営向上に有用な『経営のための会計』の講義や演習がありました。
また、講師は、現在、日本航空の再生を行っている京セラの稲盛名誉会長の経営手法及び会計理論を事例で紹介され、今から何十年も前に会長が実践していたことは、今現在も見習うべきことが多くとても参考になりました。
その中で、中小企業の皆様にご紹介したいことは、月次決算などの会計の役割・目的は、「事業をしていく過程で発生したお金やモノにまつわる伝票処理を行ない、集計をする、後追いの仕事でしかない。」と考えるのではなく、次のように考えてみてください。
① 自社の実態を正しく把握し、読み取った症状から問題を掘り起こす。
② 掘り起こした問題に、速やかに、かつ適切に対応して、自社の経営体質を強化することである。
中小企業の皆さん、月次決算などの会計は、後追いの伝票処理と考えるのではなく、経営向上に有用な「経営のための会計」として考え、経営に役立ててみてはどうですか。