-
お問い合わせ
-
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
2026/01/21

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。
インボイス制度が始まって2年が経過しましたが、今年10月から一部の経過措置について変更・終了があります。制度開始の当初とは取り扱いが変わる部分がありますので、該当する事業者の方はご注意ください。
1 免税事業者からの仕入について
課税事業者が免税事業者から仕入を行う場合、インボイスが発行されないため、仕入税額控除(注1)に制限があります。 今年9月までの仕入分は「80%」控除できますが、10月以降は「70%」に引き下げられます(注2)。
控除率が下がるため、同じ仕入価格でも課税事業者側の消費税負担が増える可能性があります。免税事業者の売上にも影響が出ることが想定されます。
注1 仕入時に支払った消費税を、納税額から差し引く仕組み。
注2 従来は50%に引き下げる予定でしたが、令和8年度税制改正大綱で、令和10年9月末までの2年間は70%とされています。
2 2割特例の終了
2割特例は、インボイス登録により免税事業者から課税事業者になった場合に使える簡易な計算方法で、売上にかかる消費税の「2割」を納税する制度です(注3)。 この特例は 令和8年9月30日を含む課税期間までで終了します。
ただし個人事業者については、令和8年度税制改正大綱により、納税額が「3割」となる特例が令和10年まで延長される方向です。
特例終了後は、本則課税(通常の計算方法)または簡易課税(売上高を基準に計算) のいずれかで申告することになります。
本則課税は仕入に係る消費税額も計算するので、事務負担が増えます。簡易課税は売上高のみで計算できるため、事務負担は比較的軽くなります(注5)。
注3 基準期間(注4)の課税売上が1,000万円を超える場合など、インボイス登録の有無に関係なく課税事業者となる期間には適用できません。
注4 基準期間は、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度(事業年度が1年の場合)
注5 簡易課税を選択できるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合です。
3 届出の必要性について
2割特例は届出不要で利用できましたが、簡易課税で申告する場合は事前の届出が必要です。 特例終了後の翌課税期間から簡易課税を使いたい場合は、その翌課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。 なお、簡易課税を選択すると、2年間は本則課税で申告することはできません。
※参照:国税庁HP
2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf
4 納税額の違いについて
2割特例は業種に関係なく控除率が一律8割でしたが、簡易課税は業種ごとに控除率(みなし仕入率)が異なります。 卸売・小売など一部を除き、簡易課税では控除率が7割以下となる業種もあるため、同じ売上でも納税額が増える場合があります。
個人事業者の場合、令和9年以降は特例の納税額が2割から3割に増えます。 小売業では簡易課税の控除率が8割であるため、簡易課税の方が有利になるケースもあります。(卸売業の場合は控除率が9割なので、今の時点でも控除率では簡易課税の方が有利です)
本則課税、簡易課税、特例のうちどの方法が有利かは一概には言えません。業種・仕入の状況・設備投資の予定などにより異なってきます。
5 専門家への相談をおすすめします
経過措置の終了に伴う対応について、税理士や中小企業診断士などの専門家がご相談に応じます。当センターの支援制度をご利用ください。
広島市中小企業支援センターHP(窓口相談)
広島市中小企業支援センターHP(経営支援アドバイザー派遣)
広島市中小企業支援センターHP(トップページ)
※事業承継税制に関する以前のブログで、「事業承継計画」の提出期限を今年3月末と記載していましたが、令和8年度税制改正大綱により、計画の提出期限は法人版(特例措置)は令和9年9月末まで、個人版は令和10年9月までとなる方向です。
※このブログは、令和7年12月末時点の法令及び令和8年度税制改正大綱に基づき記載しています。また、インボイス制度に係る経過措置に関する一般的な例について記載しており、例外的なものや細かい説明等については省略しています。個別の状況に基づく税務については、税理士・税務署に確認されることをお勧めします。
2026/01/14

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」所長の中平です。
昨年の中小企業者の皆様を取り巻く経済環境を振り返りますと、長引く物価高騰に加え、賃上げの動きが社会全体に定着するなど、コスト面での負担が経営を圧迫する厳しい状況が継続しました。また、米国による関税政策により、自動車産業が集積する広島のものづくり企業、とりわけサプライチェーンを支える中小企業の皆様にも影響を及ぼし始めており、予断を許さない状況が続いております。
さらに、本県を代表する水産資源である養殖カキが記録的な大量死(斃死)が発生し、生産者をはじめ水産関連事業に深刻な事態となっており、地域経済への影響が深く懸念されます。
一方で、本市においては、地域経済の活性化に繋がる明るい話題もありました。一昨年に開業したサッカー専用スタジアム「エディオンピースウイング広島」および商業施設「HiroPa(ヒロパ)」は、試合開催日以外も多くの市民や観光客で賑わい、街に新たな活気をもたらしています。
さらに、長らく整備が進められてきた広島新駅ビル「minamoa(ミナモア)」や路面電車の駅前大橋ルートの開業により、広島の陸の玄関を中心とした再開発が大きく進展しており、地域経済活性化への大きな追い風となることを期待しています。
このような期待と不安が交錯する大きなうねりの中だからこそ、経営者の皆様の「想い」や「悩み」に深く寄り添い、共に課題を解決し、共に未来をつくっていく存在でありたいと強く願っております。
当センターは、広島市内で活躍する中小企業の皆様をはじめ、これから創業を目指す方や創業間もない方に対して、窓口相談や専門家派遣などによるサポートメニューを整えておりますので、ぜひご活用ください。
本年も職員及びコーディネータ一同、皆様の事業発展のお力になれるよう全力で取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
2025/12/24
 おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・強口(こわぐち)です。
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・強口(こわぐち)です。
【子供との会話】
小学生の息子との会話で、勉強になったことを記載します。
少し前に鍋料理の話をしていた時、「冬に食べるのに、なんで春菊って書くんかね?」と聞かれ、しばらく考えこんでしまいました。
それまで私は疑問に思ったことがなかったのです。
ご存じの方が多いかもしれませんが、春に花が咲き、葉が菊に似ていることから、「春菊」というそうです。(旬は冬です。)
他にも息子からの質問では、「どうして、髪の毛を水で濡らすと寝癖がなおるのかね」など、私が気に留めずに過ごしているものが多くあります。
調べてみると、面白くて感心することが多いです。
子供の成長を嬉しく感じるとともに、自分の日頃の考え方や仕事への向き合い方を省みる良い機会となっています。
上記以外でも、気づかないうちに当たり前になっていて、疑問を持たずに生活していることが多くあると実感しています。
皆さんにも、よく考えると、新しい発見に繋がったり、現状よりも違うやり方のほうがよいことがあるかもしれません。
また、知らないことを知るのは、それだけでも、とても楽しいことです。
是非、些細なことでも気になることがあれば調べてみてください。
【禁酒状況】
前回ブログに記載した、家での禁酒状況の続報です。
現在も家ではお酒を飲んでいません。
そのおかげか、体調は良好で、少し前に受信した人間ドックでは、非常に良い結果でした。
お酒を扱う事業者と関わることもあるので複雑な思いもありますが、継続していきます。
なお、家以外では、時々飲んで様々な人とコミュニケーションを取るようにしています。
2025/12/17

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・久米です。
ガソリンの暫定税率を廃止する法案が2025年11月28日の参議院本会議で可決されました。これにより、ガソリンの暫定税率は2025年12月31日に廃止されることとなり、運送業の事業者の方などにおいては、経費面で大きくプラスの影響を受けるものと思われます。 私個人としても、ガソリン価格の低下は、とても歓迎しています。
では、そもそもガソリンの暫定税率とはどのようなものなのか簡単に説明しますと、1974年に道路整備のための財源として導入されたのが始まりで、ガソリン販売時に課される揮発油税などに含まれており、暫定と言いながら、長い間適用され続けてきました。
政府は、この暫定税率の廃止に向けて、2025年11月中旬から段階的に補助金を拡充していくこととしており、12月11日には暫定税率を廃止するのと同じ水準の補助金額に拡充されました。暫定税率を廃止するのに補助金を拡充するという、一見矛盾する動きのように感じますが、これは急激な価格変動による買い控えや、その反動による需要の増加など、流通の混乱を抑制するための取り組みであり、皆さんもこのことを理解して、買い控えなどはしないようにしましょう。
参考までに、ガソリン1リットル当たりの暫定税率は25.1円となっています。廃止後にその分だけ価格が下がるかというと、原油価格や為替の影響を受けるため、そのまま価格に反映されるという訳にはいきませんが、原材料等の価格が高騰している現状のなか、明るいニュースになるのものと思っています。
【2025年11月以降のガソリンの補助金拡充額】
〇~11/12 10円/L
〇11/13 15円/L
〇11/27 20円/L
〇12/11 25.1円/L
出典:資源エネルギー庁HP「ガソリンの暫定税率の廃止でガソリン代はどうなるの?...」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/zanteizeiritsu.html
2025/12/10
 おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の荒川です。
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の荒川です。
前回お知らせしたとおり新規ビジネス事業化支援事業の2回目の募集では、3件の申請があり、審査会(学識経験者、企業経営者、経営コンサルタントなどで構成)を経て、そのうち2件を採択しました。
審査会では、五つの項目(① 財務健全性、② 新規性、独自性、③ 優位性、必要性、④ 実現可能性、⑤ 発展性)について評価を行っており、申請者の方には、事業計画についてプレゼンテーション(以下「プレゼン」)を行っていただきます。
このプレゼンを効果的に行うため、当センターのコーディネータ支援の一環として、審査会前にプレゼン練習を実施しています。具体的には、所要時間を計測しながら、審査員役の複数のコーディネータが、プレゼンをお聴きし、質疑応答の後、質問に対する受け答え方、プレゼンの時間配分やプレゼン資料などについて助言を行います。
審査会当日のプレゼンでは時間制限がありますので、制限時間を肌で感じるだけでなく、説明を簡略化する項目や重点的に説明すべきポイントを再確認するためにも、プレゼン練習は有効な手段になると思います。申請者の方は是非ご活用ください。
また、申請書の作成についても、コーディネータの支援を受けることができますので、併せてご活用ください。
なお、これらの支援活用の有無が、審査に直接影響を与えることはありませんので、念のため申し添えます。
<参考>当センターのコーディネータの紹介
2025/12/03

がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・小林です。
先日、AIの活用に関する研修会を開催しました。私が講師となり、AIの活用はこれからといった創業者に向けて、AIを活用するにあたっては情報の取り扱いに注意してねといった内容です。受講者は事業を立ち上げたばかりの方や個人事業の方もいる状況での開催でした。
研修会は滞りなく実施できたわけですが、後日、気づいてしまったのです。
あ、大切なことを伝えていなかったなと_(:3 」∠)_
なので、こちらでお伝えしますw
ITを活用する際のアカウントは会社(組織)として管理してください!
ITツールは手軽に導入できるのが魅力ですが、その「手軽さ」ゆえに、開始時のアカウント登録を現場のスタッフ任せにしてしまうことがよくあります。実際、当面は問題なく動けてしまいます。
しかし、冷静に考えてみると、これは非常に危険な状態です。
スタッフに任せたアカウント登録では、当然IDとパスワードはスタッフが管理しています。
このスタッフはずっと会社(組織)にいてくれるのでしょうか?このスタッフがやむを得ない事情で退職することになったとき、アカウントは問題なく引き継げるでしょうか?不慮の事故があった場合には、もう連絡が取れないということも可能性はあるはずです。
そんな状態のITツールに、便利だからと会社の情報をどんどん蓄積させていくのでしょうか?ちょーやばいよねw
アカウント自体が会社の資産である。
この認識が抜け落ちていると、どんなに便利なツールも、いざという時に足かせになってしまいます。
ついつい「どのツールが便利か?」という機能の話に終始しがちですが、それを使うための「IDとパスワード」を会社(組織)としてどう発行・管理するのか。ここを疎かにしてはいけません。
大切であるにも関わらず、研修会で伝えていなかったことには理由があります。
それは、私の認識が甘かったから...m9(`・ω・´)ハンニンハオマエカ!
この認識の甘さに気づかせてくれたのは、実はAIですw
AIに注意されたんですよね~。認識甘いよってw
おかげ様で、また一つ考え方が整理できました。
私は今後、この問題で間違った道に進むことはありません。ありがとうAI( *´艸`)
2025/11/26
 おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・阿須賀です。
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・阿須賀です。
日本にシェアリングエコノミー協会ができたのが2015年。今や、消費者庁のサイトにも記載され、すっかり定着しています。
1 空間のシェア
2 モノのシェア
3 スキルのシェア
4 移動のシェア
5 お金のシェア
の中で、創業される方がよく使われているのは、シェアオフィス、シェアサロン、シェアキッチンなどの空間のシェアではないでしょうか。
広島でもここ数年、かなり増えてきています。自宅を公開したくない、登記する住所が必要、という住所のみの利用もありますし、来客やミーティングの場所の確保という場合もあれば、仕事をするため集中できる場所が欲しい、というケースも。中にはドリンク無料のところもあるので、冷暖房完備で自宅よりも快適かもしれません。利用時間も、24時間365日使えるものから、月の上限時間の決まったコースなどニーズによって使い方も様々。郵便ポストや宅配荷物を受け取ってくれるところもあったり、コピー機が共同で使えたり、など自宅よりも仕事しやすい環境が整っているのでは。3Dプリンターやレーザー加工などモノづくりのシェアスペースも増えてきています。
また、菓子製造や総菜・弁当など許認可取得済のキッチンを借りてマルシェなどで販売、や、飲食業許可のあるところでシェアカフェ出店、なども多く見るようになってきました。美容院やエステなどもシェアできるサロンが増えてきています。
これらのサービスは、創業の資金的なハードルを下げてくれるだけでなく、場所のもつ魅力や集客力、という違う価値を活用できるというメリットもあります。さらにそこに集まる事業者同士の交流から新しい価値が生まれる、という視点も見逃せません。
もちろん、消費者にとっても、日替わりでいろいろなお店が楽しめるというのも大きな魅力です。
また、スキルのシェアという視点で、常時雇用ではなく必要な時に必要なスキルをもつ人材を探しやすくなっていますし、副業での創業もしやすくなりました。
さらに、自社で使える物件を持っている場合は、貸会場や貸し駐車場などを登録できるサイトを活用すれば、有休スペースを時間単位で賢くお金に換えることもできたりします。
ということで、創業支援に役立つシェアサービスをコツコツ情報収集していますので、お気軽にお問合せいただければいつでも情報提供します。また、こんなところがあるよ!という情報があったらぜひ教えてください!
2025/11/19
 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・岸野です。
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・岸野です。
先日、「生産性向上に向けたDX支援の進め方」という研修に参加し、中小・小規模事業者の皆さんが抱えている経営・業務課題の整理から最適なITソリューションやアプリの効果的な導入を支援する手法について学んできました。
その中で一つ参考となった、中小企業のデジタル化やIT化をサポートするためのツール「IT戦略ナビwith」を紹介したいと思います。
「IT戦略ナビwith」は、中小機構(中小企業基盤整備機構)が運営するポータルサイトで、今年の4月に「with」という文言が追加され、バージョンアップしたそうです。内容は、簡単な質問に答えるだけで、自社のデジタル化やIT化の状況を把握できる便利なサイトとなっています。
特徴は、回答結果を基に、同業他社と比較した際の自社の立ち位置を「同業他社比較マップ」として可視化でき、IT化の進捗度合いを確認することができることと、自社の経営課題や業務上の問題点をITで解決できるところまでマップで見える化してくれる「IT戦略マップ」も自動で作成され、その解決に役立つ最適なITソリューションまで提案されるところです。
回答時間は、数分で終わりますので、「自社のIT戦略を明確にしたい」「具体的なIT導入に向けた道筋(マップ)を作成したい」とお考えの方は、一度お試しになってはいかがでしょうか 。
【関連サイト】
IT戦略ナビwith
https://digiwith.smrj.go.jp/it-map/
2025/11/12

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・竹内です。
ついこの間まで「暑いですね」と挨拶していたのに、気づけば朝夕はすっかり冷え込むようになりました。
季節の移り変わりの早さに驚くと同時に、今年も残りわずかだと感じます。
カレンダーを見ながら残りの日数を数えると...なんと!50日しかありません( ;∀;)
年末が近づくと、仕事でも私生活でも慌ただしさが増していきます。
私自身、そんな時期こそ少し早めに机の上や書類を整理するようにしています。
積み重ねた書類を見直すと、思いがけず"やり残していたこと"が見つかることもあり、改めて気を引き締めるきっかけになります。
個人事業主の方にとっては、事業年度が1月1日から12月31日までのため、まもなく決算の時期を迎えます。
帳簿の整理など、早めに準備を進めておくと年末を落ち着いて過ごせるかもしれません。
当センターでは、税理士などの専門家にご相談いただける『窓口相談』を実施しています。
経理や決算準備で気になることがあれば、お気軽にご利用ください。
https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/keiei/keiei02.html?kbn=1
2025/11/05
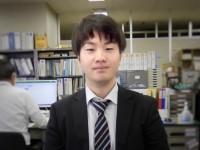
がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・平野です。
今年度(令和7年度)は経営に大きな影響を及ぼす「過去最大の最低賃金引き上げ」が行われ、広島県では時間額65円の引き上げ(1,020円 → 1,085円)が今月1日から適用されています。
皆様対応はお済みでしょうか?もしまだ求人情報の時給が1,085円以下になってしまっていたらすぐに対応しましょう。
過去の引き上げ時も経営に対する影響はとても大きかったかと思いますが、今年度の引き上げは過去最大、影響も過去最大のものになることでしょう。
実際に従業員の賃金がどのくらい変わるのか、最低賃金額で雇用しているものと仮定し、雇用形態別に2つのケースでシミュレーションしました。
週5日、1日8時間勤務のフルタイム従業員(正社員・契約社員など)
月平均労働時間 (8時間 × 5日 × 52週) ÷ 12ヶ月=約173.3時間
基本給の目安 時給 × 月平均労働時間 引き上げ前 176,766円 引き上げ後 188,090円
差額 11,324円/月
➡ 従業員一人当たり月1.1万円以上も上がることになり、複数人雇用している場合はかなりの金額になることが見込まれます。
また、基本給を基礎に、「〇か月分」や「〇を乗じて」などの計算でボーナスを決定している場合はそれも上がることになります。
週3日、1日5時間勤務のパート・アルバイト従業員
月平均労働時間 (5時間 × 3日 × 52週) ÷ 12ヶ月=約65時間
月の給与の目安 時給 × 月平均労働時間 引き上げ前 66,300円 引き上げ後 70,525円
差額 4,225円/月
➡ 従業員一人当たり月4,200円以上も上がることになり、飲食店などアルバイト・パートの方たちでシフトを組んで事業をしている場合、人数も多くなると思いますのでかなりの金額になることが見込まれます。
上記の計算は、前述の通り「最低賃金額で雇用している」場合です。なので、「うちはもともと引き上げ後の最低賃金額よりもまだ高いから影響はなさそう」と感じられる方もいるかもしれません。
ですが、従業員の視点に立ってみると、「世間では過去最大の最低賃金引上げだって言っているのに、私たちは給料が1円も上がらないな・・・」という不満やそれによるモチベーションの低下が発生する可能性が高いです。
なので結果的に、少なくない影響がすべての従業員を雇用している企業に降りかかることになります。
これまでもベースアップ(全従業員の基本給の水準を底上げすること)などに取り組まれてきた企業の経営者にとっては、「また上げなきゃいけないのか・・・」と悩まされることと思います。財務状況が悪化する前に、賃金に対しての対応だけでなく、商品・サービスの価格から経費まで、全体の収支やビジネスモデル自体の見直しをする必要があるかもしれません。
厚生労働省が実施している業務改善助成金やキャリアアップ助成金などの賃金引上げ等に関連する助成金もありますので、この機会に活用してみるのも良いかと思います。
もしも、この度の最低賃金引き上げやそれに伴う事業全体の見直し、助成金の活用に関してお悩みでしたら、専門家に無料で相談できる窓口相談などもありますので、ぜひ当センターをご利用ください。