-
お問い合わせ
-
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
2025/09/24
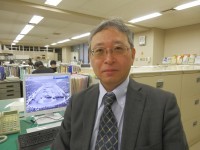
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・姫野です。
近年、Webサイト(ホームページ)を持つ事業者が増えています。事業内容や所在地などをインターネット上で確認できることから、Webサイトは事業活動において欠かせない広報媒体と言えるでしょう。
SNSで代用されるケースもありますが、Webサイトは「公式サイト」としての信頼性が高く、SNSと連携することで集客効果をさらに高めることが可能です。
さて、皆様はWebサイトの制作や運用をどのように行っていますか。おそらく、多くの方が制作会社など外部の事業者に委託されているのではないでしょうか。
近年は定型化(テンプレート)や自動化(自動でインストール)が進み、ある程度の知識があれば自作も可能になってきましたが、それでも専門的な知識やスキルおよびセンスが必要な場面は多く、依然としてハードルは高いと言えます。
Webサイトを公開するには、まずレンタルサーバー(以下「サーバー」)を契約し、ドメイン(インターネット上の住所のようなもの)を取得します。そのうえで、表示する文言や画像などのコンテンツを制作し、Webページとして構築。これをサーバーにアップロードし、必要な設定を行うことで、初めてブラウザ上で閲覧できるようになります。
しかし、Webサイト制作を外部に委託する際には、契約・運用・技術・法務など、さまざまな面でリスクが潜んでいることは意外と知られていません。特に注意すべきは、契約や権利関係にまつわるリスクです。
さあ、Webサイトを作ろう!と意気込んで、委託業者とはサイトの内容と費用の話しばかりをして肝心な契約内容がおざなりになった結果として、たとえば、以下のようなトラブル事例があります。
- 著作権が制作会社に帰属しており、改変や再利用ができず、他のサーバーへ移転できない
- ドメインやサーバーが制作会社名義で契約されており、移管を拒否されたり高額な費用を請求された
- 契約書が存在せず、納期・費用・修正範囲などで認識の違いが生じた
- 著作権侵害の可能性がある素材を使用しており、改変や再利用ができない
- ライセンス違反の素材(画像・フォントなど)を使用していて、第三者から訴えられた
- 品質やセキュリティの問題が放置され、Webサイトが乗っ取られたり情報漏えいが発生した
このような事態を防ぐためには、どうすればよいのでしょうか。
まず、制作会社とは必ず契約を締結してください。口約束での依頼は避けましょう。契約前には、特に以下の点を確認することが重要です。
■サーバー・ドメインの帰属に関する注意点
- サーバー契約者の名義が自社か制作会社かを確認する
- サーバーの管理権限(FTP、CMS、メール設定など)が誰にあるかを明確にする
- ドメインの契約者名義(Whois情報)を確認し、自社名義であるかを確認する
- サーバー費用の支払い主体(自社か委託先か)を把握する
- サーバー移管の可否と手続き方法を事前に確認する
- 障害対応や保守体制の有無と範囲を確認する
- ドメインの管理権限(DNS設定、更新など)が誰にあるかを明確にする
- ドメインの更新費用の支払い主体を確認する
- ドメイン移管の可否と手続き方法を確認する
- ドメイン失効時のリスクと対応策を共有しておく
- 契約書や覚書に、サーバー・ドメインの所有権が自社にあることを明記する
- 委託終了後も自社で継続利用できることを契約上保証する
- 管理情報(ID・パスワード)の引き渡し条件を明確にする
- トラブル時の対応責任と連絡体制を事前に合意しておく
■著作権・素材の取り扱い
- 使用する画像・イラスト・動画・音源などの権利関係を事前に確認する
- 制作物(デザイン、文章、プログラムなど)の著作権が誰に帰属するかを契約書で明記する
- フォントや写真などの素材が商用利用可能か、ライセンス条件を確認する
- 外部提供素材(ストックフォト、テンプレートなど)の使用範囲や再利用可否を把握する
- 制作会社が独自に用意した素材の出所とライセンスを確認する
- 著作権侵害が発生した場合の責任の所在を明確にしておく
- 納品後に自社で使用・改変・再利用する際の制限があるか確認する
- クレジット表記や著作権表示が必要な素材が含まれているかを確認する
盛りだくさんの内容ですが、これらはほんの一部です。契約書にこれらの事項がきちんと明記されているかどうかを必ず確認したうえで、契約してください。
本来、サーバーやドメインは依頼者側(自社)に権利があるべきものですが、契約内容によっては制作会社側に権利があると主張されるケースもあります。
場合によっては、サーバー上のコンテンツやプログラムを修正する必要が生じることもありますが、契約内容が不明確なまま手を加えると、「勝手に改変した」としてクレームや費用請求につながる可能性があり、非常に危険です。
状況によっては、正直なところ、一から作り直した方が早くて確実な場合もあります。
「安かったから」「親切そうだったから」「知人の紹介だったから」・・・その結果、費用も信頼も失ってしまうことのないよう、慎重に進めましょう。
万が一トラブルに巻き込まれた場合は、当センターの窓口相談で弁護士相談などをご活用ください。
2025/09/17

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。
資金調達の方法として、近年クラウドファンディングをよく耳にするようになりました。今回はこのクラウドファンディングによる資金調達について、税金の取り扱い(資金調達側)を見てみます。
クラウドファンディングは、①購入型、②投資型、③寄付型の3つの型がありますが、それぞれで取り扱いは異なります。
1 購入型
購入型については、売上と同様に考えることができます。調達した資金は、資金調達時には「前受金」となり、商品・サービス等のリターンを行った時点で「売上」となり、益金又は収入に算入されます。なお、クラウドファンディングの手数料はその発生時点で損金又は経費に算入されます。また、「売上」となった時点で消費税が課せられます。
2 投資型
投資型クラウドファンディングは「融資型」、「株式型」が主なものですが、融資型は借入金、株式型は資本金と同様に考えることができます。調達した資金については、負債又は資本金なので法人税、所得税、消費税は発生しません。クラウドファンディングに係る手数料や(融資型の場合の)支払利息については、損金又は経費に算入できます。
3 寄付型
寄付型では、資金調達者が個人か法人か、資金提供者が個人か法人かにより、税務上の取り扱いが変わってきます。以下、それぞれの場合について見てみます。
(1)資金調達者が個人の場合
資金調達者が個人の場合、資金の提供者が個人か法人により関係する税目が変わります。
①資金提供者が個人の場合
この場合は贈与税が適用されます。資金調達額とその年中に受けた他の贈与額とを合算した金額をもとに贈与税額が計算されます。なお、資金調達額(贈与額)からクラウドファンディングに係る手数料は控除できません。
②資金提供者が法人の場合
この場合は所得税(一時所得)が適用されます。一時所得なので次の算式により計算した金額が、所得金額に加算され所得税が計算されます。
(調達額―手数料等の経費―50万円(特別控除額))×1/2
※他に一時所得及びその所得に係る経費があれば、それぞれ調達額、経費に合算されます。
(2)資金調達者が法人の場合
この場合は法人税が適用され、資金調達額は受贈益として益金に算入されます。手数料等の経費は損金に算入されます。
ここでは一般的な例で記載しており、詳細や特別な場合等については省略しております。個別の事情により税務上の取り扱いが変わる可能性もありますので、実際にクラウドファンディングで資金を調達される際には、税務署や税理士に確認されることをお勧めします。
当センターでは税理士等の専門家が皆様からのご相談にお答えします。皆様のご利用をお待ちしております。
広島市中小企業支援センターHP(窓口相談)
広島市中小企業支援センターHP(経営支援アドバイザー派遣)
広島市中小企業支援センターHP(トップページ)
※当ブログは令和7年9月1日時点の法令等をもとに記載しております。
2025/09/10

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・久米です。
最近、企業の方から人手不足や人を採用してもすぐにやめてしまうなどの話を聞くことが多くなりました。帝国データバンクが出している人手不足に対する企業の動向調査(2025年7月)によると、正社員では50.8%の企業が人手不足と感じており、業種別にみると、建設業、情報サービス業、運輸業などでは6割を超える割合となっています。また、働き方改革や2025年6月から義務化された熱中症対策など、いろいろ制約がある中での人手不足は、事業を行っていくうえで大きな支障となっています。
このような状況のなか、人を採用するに当たり、賃金の引上げや福利厚生面の充実、教育体制の整備による幅広い人材確保など、企業側もいろいろ取り組んでおられるかと思いますが、就職希望者に自社を選んでもらい、継続して働いてもらうためには、その会社に入るとどのようなキャリアを形成することができるかをしっかり伝えること、仕事を行う際に会社の経営を意識させることが重要であると考えています。賃金などの待遇面ももちろん重要ではありますが、将来の自分がイメージできることで、ミスマッチになる可能性は少なくなり、自分の仕事が会社にとってどのような役割を果たして、経営にどう影響しているのかが明確になれば、仕事に対するモチベーションも変わってくると思います。また、会社に模範となる社員がいれば、その人物を紹介することで、それを目指して希望者が出てくるかもしれません。
特に中小企業の方にとって、良い人材の確保はその後の経営に大きく影響を及ぼすことから、このような切り口で採用に取り組まれてみてはどうでしょうか。
出典:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年7月)」
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250819-laborshortage202507/
2025/09/03
 おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の荒川です。
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の荒川です。
昨年度まで実施してきた「新成長ビジネス事業化支援事業」の対象分野の制限を撤廃し、「新規ビジネス事業化支援事業」としてリニューアルしたことは以前お伝えしたところですが、今回は、その募集結果についてです。
4月の募集では9件の申請がありましたが、そのうち6件の申請が取り下げられ、残りの3件について審査を行った結果、3件すべてを採択しました。
申請取下6件は過去最多であり、その理由のほとんどが「早く販売したい」というものでした。
というのもこの事業は、開発した試作品の事業化までを支援するものですが、販売=事業化と見なすため、事業認定日から販売日までに支払いを完了したものが補助対象経費となります(販売日か翌年2月末日のいずれか早い日まで)。販売時期が早くなればなるほど補助対象経費にできる期間が短くなり、申請締切から事業認定まで約2か月を要することを合わせて考えると、補助金を受けるメリットが小さくなります。また、申請すると、審査会でのプレゼンと事前のプレゼン練習の2回、当センターに来所する必要があります。販売時期とこれらを総合的に判断した結果、申請を取り下げられたのではないかと考えています。
こうしたことから最終的な申請は3件になりましたが、問合わせ件数や当初の申請件数は、昨年度以前より増加しており、対象分野の制限撤廃による一定の効果はあったものと思っています。
先に3年ぶりに行った第2回の募集でも3件の申請があり、現在、審査会の準備を進めているところです。(このブログが公開される頃には、審査会を終えている予定です。)
これからも、利用しやすい制度となるよう、適宜見直しを検討してまいりますので、現行制度の利用しにくい点など、お気づきの点がございましたら、お気軽に当センターまでご連絡ください。
<関連リンク>
https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/joseikin/shisaku.html